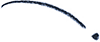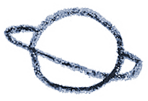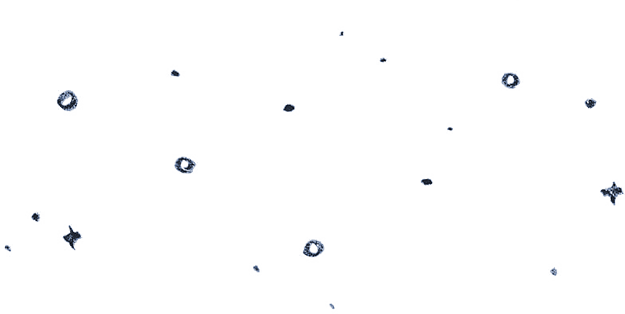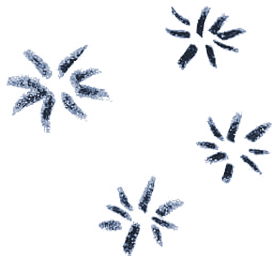文=屋代忠重
フランスからスペインの田舎に移住して農園を運営する傍ら、廃墟となった古民家を改修して新しい移住者を集めようと奔走するアントワーヌとその妻オルガ。村の秩序を乱すよそ者として、夫妻を警戒する兄のシャンと弟のロートン兄弟は村の有力者でもある。風力発電の土地買収による住民投票の結果をめぐり、この隣人どうしの軋轢が決定打となり、やがて重大な事態へと発展していく。まるで日本で実際に起きた事件を元にしたルポ「つけ火の村」を彷彿とさせるような、都会からの移住者と長年住みついた者たちの深刻な対立は、決して一元的な理由で深まったわけではない。もともとパリの大都会で暮らしていた夫妻(アントワーヌにいたっては世界中を旅する時間と金銭的余裕まであった)と、何十年とスペインの田舎で強権的な父親に支配され、選択肢自体を持たされなかった兄弟とでは、根本的な価値観が違いすぎる。これを無視して兄弟たちを一方的に非難するのは些か不公平といえよう。
風力発電の土地買収でまとまったお金が手に入ると分かったとき、初めて兄弟は「ひょっとして自分たちの境遇は惨めなのではないのか?」と気づいた。この時、買収に反対した夫婦たちに対して、兄弟が抱いた憎悪は想像に難くない。アントワーヌからすれば、手に入る金額なんて微々たるものだし、それを元手に兄弟が都市へ出てタクシー運転手をやっていく計画を聞かされても、無理なのは分かっている。そのことを諭されても、兄弟が彼から見下されている、侮辱されていると感じてしまうのも無理はない。映画冒頭では兄弟が野生の馬を力ずくで押さえこむシーンが描かれている。これまで力を見せつけることで村内のヒエラルキーの上に立ってきた自分たちが、都会から来たよそ者の意見に屈すること自体が屈辱なのだ。兄弟が井戸に自動車のバッテリーを投げ入れ、夫妻の畑を全滅させた行為が、有力者である兄弟一家の荒廃していく村に対する影響力を示唆している。きのうきょうで住みついたアントワーヌに「この村は俺の家だ」と言い放たれたことに殺意さえ抱いただろう。実際、同じく長年この村で暮らすペピーニョは、風力発電に反対の立場を取っていたし、夫妻とも懇意であったが、兄弟は彼を咎める姿勢はみせていない。移住者を募って村を再興しようと計画する夫妻からみれば、いくら人が減って村が荒廃しようと構わず、自分たちの日々の暮らしだけに執着する人々は、社会の維持を放棄した単なる獣にしかみえないのかもしれない。あれだけ笑顔だった妻オルガの表情は、徐々に獣たちに怯える顔つきになっていく。
アントワーヌを中心に描かれた前半に変わって、後半は妻オルガを中心に描かれる。夫妻と離れて暮らしていた娘のマリーは、ある事件をきっかけに度々村を訪れるようになる。そこでの生活を通して、オルガと娘のこれまで見えなかった軋轢が炙り出される。映画全体を通して、レタスの葉を剥ぐように少しずつオルガの人間性が露わになっていく。シシュポスの岩や賽の河原のように、救いが訪れるとは思えない村の暮らしに執着する母を娘はなじるが、羊の引き渡しでみせた母の覚悟をみて理解するようになる。そして母娘は和解こそするが、村での生活を選んだ母と、村を離れて一緒に暮らすことを望む都会的な娘、互いの決して交わらない生き方に深く嘆き悲しむのである。これは構造的にアントワーヌと兄弟の関係性に近いが、両者が遂に和解できなかったのとは対照的である。そして終盤でオルガとある人物が、実は似た境遇であることに気づかされる。しかし二人の差は紙一重でありながら、人と獣を分かつ大きく厚い壁でもあった。ラストシーンでみせた微笑は、その残酷さをありありと物語る。まるで煉獄のような村の暮らしを祝福するかのように。
35thTIFF 2022/10/26

作品情報
監督:ロドリゴ・ソロゴイェン
キャスト:ドゥニ・メノーシェ/マリーナ・フォイス/ルイス・サエラ
138分/カラー/スペイン語、フランス語、ガリシア語/英語・日本語字幕/2022年スペイン、フランス
予告編はこちら
妄想パンフ
・正方形の判型サイズで、表紙は映画冒頭の男達に押さえつけられた馬の鼻が見えるシーンを採用。真ん中にタイトルを配置して、村の息苦しさや閉塞感を暗示している。