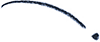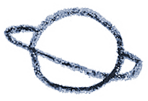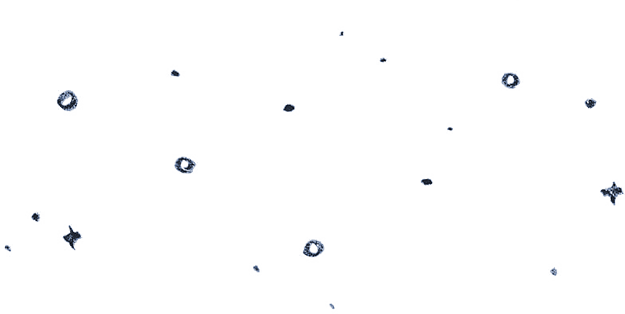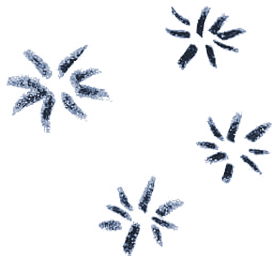文=竹美 イラスト=あずさ
今回の作品は、90年代後半から一世を風靡したファッションブランド、アバクロンビー&フィッチの盛衰を描くドキュメンタリー映画である。作品は、同社のブランド戦略を分析しながら、同社で不当な雇用差別に遭った元従業員たちによる訴訟、アジア人蔑視的なロゴに対する非難、続いてCEOの外見至上主義(ルッキズム)的な発言に対する批判運動の顛末を描く。
例えば、あなたがあるアパレルメーカーに採用されたにも関わらず、何故か店舗のシフトに入れない。何故だろうかと探っていくと、実はそれが「あなたの容姿が店舗の戦略と合致しないから」という理由だったとしたらどうだろう。そこに人種主義が絡んでしまっているとしたら。そのようなことが明るみに出た結果、訴訟が起きている。
また、アバクロのような大企業が、アジア人のことを揶揄するようなステレオタイプ的なロゴをあしらったTシャツを「面白いでしょう?」とばかりに販売していたら、許しがたい気持ちになるかもしれない。今住んでいるインドでは、私の容姿をしげしげと見る人が時々おり、「チャイニーズ」と遠回しに言う人もいる。私は気にしないが、本当に中国人だったらどんな気持ちになるだろうか。
また、CEOのマイク・ジェフリーズが外見至上主義的な発言をしていたことも、後から明るみに出てしまい、猛非難を受けてしまった。太った人間は醜いからアバクロを着なくてもよろしいと言われたらどう思うだろうか。
最後は、写真家として起用されていたゲイの写真家ブルース・ウェバーが、若い男性のモデルたちに対して行ったとされるセクハラ疑惑が訴訟沙汰になったことが取り上げられた。一方CEOのマイク・ジェフリーズについてそのような訴えは起きていない、というテロップも出て来る。また、ジェフリーズを雇った昔のアバクロの元経営者に関してもスキャンダルが明らかになってしまった。ダメ押しで、ヒジャブを被る女性に対してまで雇用差別を行った件も明るみに出た。その価値観の排他性を指摘され、満身創痍のアバクロは、よりインクルーシブな価値観を体現するブランドに生まれ変わることができるだろうか。作品はそれに対してやや懐疑的な態度を見せて終わる。
では、問題だらけだったと指摘されるアバクロの戦略はどういうものだったのだろうか。『ホワイト・ホット』という題名の通り、同社は、眼や髪の色の明るい、筋肉質で締まった体形を持つ白人男性の若く健康な身体を全面に出した広告を展開し、店舗展開もそれに準じた(故に差別的な対応が行われた)。
ところでアメリカンカジュアルの服の広告というものは、2004年当時住んでいた韓国ですら、健康的な白人の男女が満面の笑顔で身体を躍動させる広告が使われていた。当然日本でも同じ光景を見て来たし、今のインドですら、平均的なインド人の肌の色を無視した形で類似した広告展開が見られる。つまり…
白人=ホワイト(の男性)はホットなのだ!
という考えを、多くの人が面白くないと思いつつ、受け入れている。その結果として白人の男性は他の人種の男性よりもホットだ、と我々が判断してしまうのだとしたら、それは、そのような価値観を垂れ流す企業等のせいでもある一方、受け取り手のリテラシーの問題でもある。
若い白人男性の美しさをアメリカの上流層のイメージと結び付けた広告戦略が人気の秘訣でもあり、一部の人々に嫌われた理由なのだろう。作中取り上げられた人物の発言はそれを教えている。その女性は、初めてアバクロの店舗に行ったときに、「私が高校時代に嫌いだったものが全てそこにあった」と感じたと述べている。つまり、人気があった裏では同じくらい嫌われていたのだろう。
一方、訴訟が起こされても尚、アバクロは、CEOマイク・ジェフリーズのいささか偏った信念を忠実に表現し続けた。自分の好きなものを追求するという行為には、必ず選別と線引き(言い換えれば差別)が伴う。美が絡んでいるからこそ、ファッション自体が持っている排他性は露骨に現れて来る。それ故に皆が憧れ、好きで購入するのである。しかし、憧れても憧れてもそこに入れない人がおり、やがてその心には影が生まれる。
本作ではアジア人のブロガーや、有色人種でかつて太っていたゲイの「活動家」の事例も取り上げられている。アバクロを非難するような言葉をSNSで投稿したら、一晩のうちに盛り上がって署名が集まり、アバクロに直談判に行くことになった、という体験談がいかにも今らしい。彼らは、声を上げられなかった弱者の怒りのパワーが、SNSやネット上で集結し、遂に差別的な巨大企業に一矢報いたのだというエンパワーメントの物語を生きている。差別的な採用基準や商品について会社がその常識を問われることは当然だ。一方で、同作がまさにその声を拾っている通り、アバクロには元々「何となく面白くない」と思っていたアンチ層が存在したということも見逃せない。ジェフリーズの容姿について罵倒する発言が噴出するシーンを観ると、運動の後半は、アンチ層の働きによって成功したように読めるのである。この件を雇用差別と同列に扱っていいのかどうかは疑問の余地があると私は考える。
ところで、アバクロは、日本に展開するより前の90年代後半の時点で、日本のゲイにも人気があった。ブルース・ウェバーを起用した広告戦略は、即座に太平洋を越えて日本のゲイに伝わっていたのである。COEのジェフリーズは自身が同性愛者かどうかを明確にしていない。彼が同性愛者だとする同作の説を採用すると(「差別主義者」にはアウティングへの配慮が適用されない模様)、ジェフリーズの憧れが何となく理解はできる。作中で流れた同社の広告ビデオからにじみ出ていたのは、白人の体育会系男子特有のいかつい熱気だ。それを演出したのが同性愛者の2人だったというのだというのは説得力がある。男性性に憧れてもそれになり切ることができないという葛藤は、多くの男性同性愛者が体験している。『パワー・オブ・ザ・ドッグ』のフィルがブロンコ・ヘンリーを模倣してしまう気恥ずかしさと同種のものを連想してしまうのは私だけだろうか。彼らは美しい「夢」を完成させ、あまりに純粋すぎる憧れの結晶(「夢」は偏っている!)が、一部の人を怒らせたり傷つけることになり、結局自分の首を絞めることになってしまったと読めるのである。
アバクロに対する批判の署名を持ち込んだ活動家は、アバクロという悪のゲイの要塞に戦いを挑んだ若いゲイのジェダイのようだ。一方彼はSNSの支持をバックにしているが故に、慎重に自己管理をしなければならない。若い活動家たちは、人前に出ることで視線を集め、否応なく磨かれ、憧れの対象となっている。今、社会的な問題を告発する若い活動家こそが「ホット」だ。そして、彼らへの憧れを抱く者の心には、嫉妬のような影の感情をも生み出すだろう。悪役になり下がったアバクロの辿った道と似ていないだろうか。我々が今、何も考えずに新しい「ホット」に酔い痴れているだけなのだとしたら、やがて我々の中から反発や離反が起こるだろう。これはそういう「皮相な」現象ではないのだ、と私も信じたいが、ジェフリーズの容姿に対する罵倒については全く配慮の無い同作を見るにつけ、何かが気になってしまうのである。
作品情報
監督:アリソン・クレイマン
時間:88分
製作国:アメリカ
製作年:2022年
ドキュメンタリー作品
Netflixにて配信中