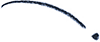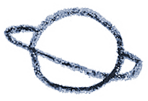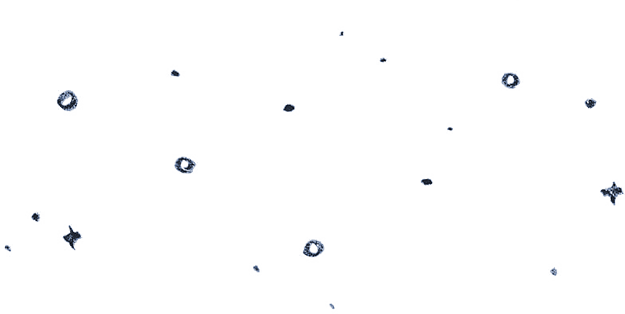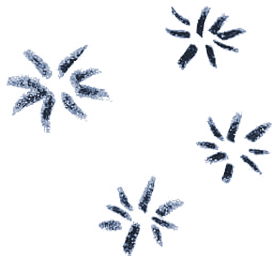文=浦田行進曲 妄想パンフイラスト=映女
小学生の頃に一度、酪農体験が出来る宿泊イベントに参加したことがある。単身牧場に乗り込んだ私は、他校から来ている年上の2人組に何が気に食わなかったか目をつけられ、いじめられそうになった。危機回避のため自由時間の度に私は誰もいない牛舎へと向かった。牛という動物は、その臭いや飛び回るハエから子どもたちから人気がなかったのだ。
特にやることもないので牛の絵を描いて過ごすことにした。観察を始めると乳牛たちは1頭1頭違う柄を持ち、黒くて丸い目が可愛らしいことを知った。手を伸ばすと温かい鼻息を感じて、この動物のことが大好きになった。
『牛』(原題『Cow』)というシンプルなタイトルの本作は、ルマと名付けられた雌牛の半生を追ったドキュメンタリーだ。動物、生き物のドキュメンタリー映画と言えば『ディープ・ブルー』、『皇帝ペンギン』、『ミクロコスモス』など話題となった作品も多い。直近では第93回アカデミー長編ドキュメンタリー賞を受賞した『オクトパスの神秘:海の賢者は語る』が、1匹のタコにほぼほぼ恋情を抱く男性の写した記録映像となっており異色の作品だった。
『牛』のユニークな点は、ナレーションがないことだ。牛の気持ちを勝手に代弁するような台詞がないのはもちろん、彼らの生活に対する説明さえ存在しない。言葉は牧場で働く人々の、必要最低限の会話と牛たちに対する呼びかけのみ。また、カメラは常にルマ、もしくは彼女の産んだ仔牛の目線と同じ高さで動く。題材として肉用牛ではなく乳牛を追っているところも面白く感じた。(我が家では内容を知らずクリスマスにご馳走を囲みながら家族で藤子・F・不二雄の『ミノタウロスの皿』のアニメを観てしまい、とんでもない空気になったことがある。)
映画はルマの出産シーンから始まり、前半は彼女とその仔牛を、世話をする人間側の視点に重きを置いて追っていく。右腕を肘まで突っ込んで子宮口を触診したり、蹄を道具を使って研磨したり、ツノの位置に焼きゴテのようなものを当てブルーの液体をかけたりする映像を観ているうちに、いつの間にか視点はルマのほうへ寄り添うようになり、彼女が食む草の匂いや夜風を共に感じている。
牛という動物は穏やかなイメージが強かったが、想像以上に表現豊かな生き物だと知った。しかし例えばその鳴き声ひとつ取っても、悲しんでいるのか怒っているのか、もしくは喜んでいるのかいかようにも聞こえて知識がない者には判断が出来ず、具体的な感情を読み取るのは難しい。「寂しそうな眼をしている」といった、こちら側が感情を当てて見ることはいくらでも出来るが、正しくない気がする。
そうしたキャラクター化が難しい存在ながら、並行してまるで『ベイブ』のように、ルマが主役のドラマとして魅せているのが本作の稀有なところだ。
私は子どもの頃の数日出会ったあの牛の顔を今でも覚えているし、彼女を描いたスケッチブックを覗いてきたいじめっ子の片方が上手いやん、と呟いたというオチもあって元々相当に牛への思い入れの強い人間だと思うが、そうではない人々も『牛』を観ていただければこの動物の魅力に心を掴まれることだろう。

妄想パンフ
A4縦判型で表紙は白地に黒抜きで表題 COW の記載と牛の姿のみのシンプルな表紙に。

作品情報
『牛』(原題: Cow)
予告編はこちらから
監督:アンドレア・アーノルド
94分/カラー/英語/日本語字幕/2021年/イギリス