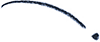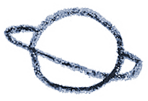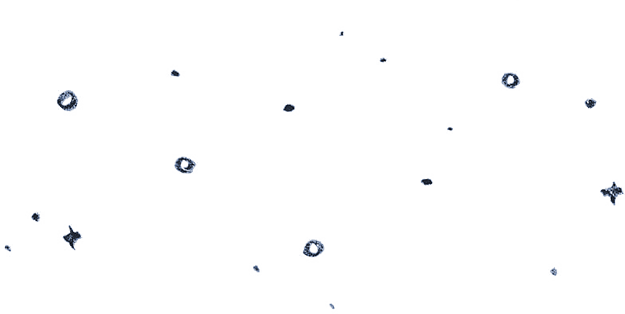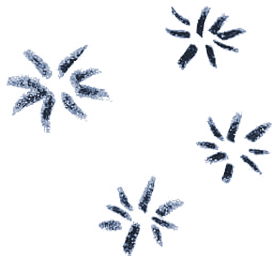文=竹美 妄想パンフイラスト=ロッカ
「彼は頑張っていたよ」
欧州映画を勝手につないでみると、EU経済とは何なのかが分かってくる。EUの勝ち組ドイツの映画『ありがとう、トニ・エルドマン』(2016年/マーレン・アデ監督)では、女性コンサルタントがルーマニアで一旗揚げようと奮闘、彼女達エリートが吸うコカインはイタリアのマフィア経由で欧州に入り(『皆はこう呼んだ、鋼鉄ジーグ』(2015年/ガブリエーレ・マイネッティ監督))、ロンドンからイタリアに帰国した女性建築家は男尊女卑の壁に阻まれ(『これが私の人生設計』(2014年/リッカルド・ミラーニ監督)、海千山千(笑)のルーマニア出身のゲイ青年はイギリス農村の若者のハートと自らの落ち着き先を勝ち取る(『ゴッズ・オウン・カントリー』(2017年/フランシス・リー監督))。今回の『私は決して泣かない』は、ポーランドからアイルランドへの出稼ぎ現象を描いている。
ポーランドに住むオラは17歳、自分の車が欲しい。それなのに4回目の運転免許の試験に落ちた上、アイルランドに出稼ぎに行ったっきり疎遠な父親は職場で事故死。英語のできない母親はオラに、アイルランドに行って遺体を持ち帰るよう命じる。あたしの車はどうなるのよ…。
父が死んだと聞かされても、ほとんど一緒に暮らしていなかったために父の記憶も無く、全く興味のないオラと、泣きぬれる母親との温度差。父親の事故死を知らせる電話がかかってきても何を言っているか分からない母親に代わり、英語が堪能なオラが電話で応対する。この形でEU後進地域の家族は分断に慣れっこになっているのかもしれない。
しぶしぶアイルランドに渡ったオラは、お金が無いから火葬にして遺灰を壺に入れて持って帰るとドライに話すが、母親は「お葬式は土葬じゃないとだめ。火葬なんて叱られる!」と文句を言い始める。後の方のシーンでも火葬には否定的な目が向けられている。EUの中で「故国に残る」ということは、現地文化を強く持ったコミュニティの中で生きるということなのだと示唆している。その温度差は、EUの中の静かなきしみになっているのではないかなと思った。その中で、アイルランドも出稼ぎ先になっているのだというのも初めて知った。
アイルランドの職業紹介所で働くポーランド人のおじさんの言葉には、移民した先で頑張るポーランド人の苦労や悲哀がにじむ。父親が残した金で、「私の代わりにおじさんが車買ってキープしといてよ」と頼むオラに「ポーランド人は皆そうだ!お金送れ送れってそればかり!働いてお金を送る父親の身にもなってみろ!」と憤るが、何だか狼狽しているようにも見える。なぜって彼はそういう「金をせびられる父親等」に仕事を紹介する形で、彼らの上に君臨している上、息子には英語で話しかけ、彼にはポーランド語を使わないのだから。
分断家族はもう元には戻らない。オラは、「保険金払え」と事故のあった職場の上司にかけあっていたが、段々父親が気になって来たのでどんな人だったのかを問うが、「ここでは誰も自分のことは話さない。だから私にも分からない。でも彼は頑張っていたと思う」と言われる。
「彼は頑張っていた」。その言葉が自然に口をついて出てきた後、偶然の出来事によって自分が手にしているものに気が付いたときのオラの表情に泣かされた。無関心、恨み、憤り、不満、嫌悪…オラはありもしなかった父親との関係や、知りたくなかった父の姿に涙することはできない。でも家族だからという理由では全く愛せない父親を「遠い場所でそれなりに頑張って生きた誰か」として想像することはできる。
家族のため、自分のため、誰かを支えるために頑張って生きているのはどこでも、誰でも同じなのだ…観終わった後に不思議な連帯感がわく。全くの他人の苦しさや哀しさ、小さな幸せ等を想像してみることは、この分断の時代にこそ必要なのではないだろうか。
妄想パンフ

作品情報
監督:ピョートル・ドマレフスキ
キャスト:ゾフィア・スタフィエイ、キンガ・プレイス、アルカディウシュ・ヤクビク
100分/カラー/英語、ポーランド語/日本語・英語字幕/2020年/ポーランド・アイルランド