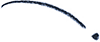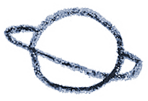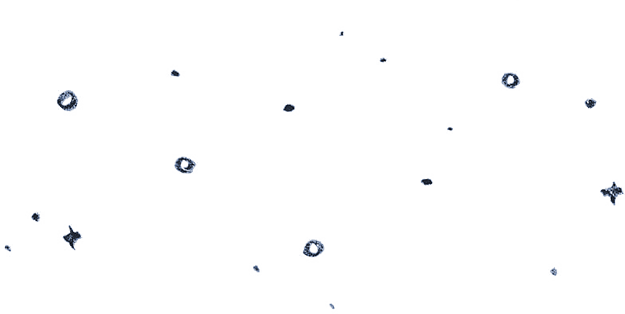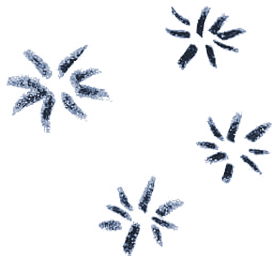文=きゃさ
映画は、短ければ短いほど、好きだ。
これは、そのままの意味で、映画の時間が90分以内であると、それだけで観てみようと思えるし、たとえ何時間の映画であろうと、自分の中での感じ方があっという間であれば、それは「短い」という意味で好きだ。
映画を観たいけれど、そこまで余力がないときが多い。だから、短い映画を選ぶことが多い。
さらに、今のこの状況の疲弊も相まって、映画を観ることがより心理的に遠のいている。
そんな私が最近、なんとか観ることができた、短い映画やショートフィルムについての、感想とも言えない端書きをつらつらと。
この状況に際し、限定配信してもらえている作品も多い。主にそうした作品にを挙げながら、作品ごとのテンションで書いたものです。
※限定配信等が紹介されている、参考記事はこちらです。随時更新されています!
4月8日(水)
ノア・バームバッグ『フランシス・ハ』(2012年/86分)
ノア・バームバッグは、なんでこんなに感情を描けるのでしょうか…。
ずっと、観よう観ようと思いながら、先伸ばしていた一本。
主人公・フランシスはずっとバタバタと走っている。親近感。
ラストは映画のタイトルの理由が明かされるが、彼女のずぼらさが肯定される感じがとてもいい。
現代劇のモノクロで一番に思い出したのは、サム・フリークスという上映イベントで観た『まどろみのニコール(原題:Tu dors Nicole)』(2014年/93分/ステファヌ・ラフルール)。
「じぶん的に、完璧!」という雑すぎるメモしか残っていないのですが、テーマ、登場人物、編集、音楽が最高にどツボでした。名画座で二本立てとかで観たいですね。

4月11日(土)
池添俊『愛讃讃』(2018年/8分)
5月6日まで限定配信予定の、数々の映画祭で賞を受賞したショートフィルム。
「幼年期の継母の奇妙な影響を記憶以上に詩的に表現した」ものである。以前から気になっていた作品。でもこれは、是非フィルムが観れる映画館で、観たい…。
おぼろげな記憶、部分的にうつる顔のパーツ。燃えるような火鍋の記憶。どきりとしてしまう、出会いについてのことば。
一番心をもっていかれたのが、カラオケのシーン。カラオケで歌う継母(の壁側?)に、カラオケの映像と歌詞が重なっている。
カラオケの、虚に虚を重ねるような感覚。しかし、歌う人の声によって、その歌はその人の歌になり、その歌詞が本人に憑依する、ドキュメントになる。
これはカラオケをただエモく言っているだけなのかもしれないけれど、他人が書いた歌詞も、その人の声を通して歌うことで、その人の身体感覚が重なる。
カラの音楽に、棒読みで流れてくる歌詞も、歌声によって突然、誰かの事実になるような。そうした、突然立ち現れる身体感覚みたいなものが、あのカラオケシーンによって、ぐいと引き込まれる。突然この映画が、じぶんの何かしらの記憶を呼ぶ。気付くと、この映画の中に完全に立っているのだ。
映画におけるカラオケシーンといえば、『きみの鳥はうたえる』、『慶州 ヒョンとユニ』がまず浮かぶ。
上ほどの感覚にはならずとも、どちらも歌にぐいぐいと登場人物たちが入っていく。
こういうところで出会った音楽は、カラオケのレパートリーに入れたくなりますね。(「オリビアを聴きながら」を聴きながら)

4月12日(日)
瀬田なつき『あとのまつり』(2009年/19分)
「あとのまつり、全部フェスティバル!」やかましい、騒がしいほどの多重層な映画。
「映画には、鏡と踊りがだいたい出てくる」という友人のことばを思い出した。(この映画に鏡は出てこないけど)
走る、踊る。指先の切れた血で唇を拭うのは、『ミツバチのささやき』?風船は『赤い風船』?
走るはカラックス、踊るはハルハートリー?赤いパーカーは『E.T.』?00年代の服のダサさのドキュメント。目覚めのキス。記憶、記録。
ものの、ひとの、行為の、運動が、個人の映画の記録につながって、映画を映画たらしめるもの、として存在する。
きっと上の羅列は浅はか、短絡的。自分が映画を観てきていないことが、わかってしまう。
この時間のなかでも、映画たらしめるものが散らばっていれば、すごく壮大な映画として立ち上がる、気がする。
それはただの記号論、象徴、連想ゲームなのかなあ。太賀が出演してる、濱口竜介も製作に関わっている。すごく面白かった。
4月13日(月)
友人が監督した、15分ほどの短編を観た。ずっと前に送ってくれていたのに、観そびれていた作品。
おそらく彼女の経験が色濃く反映されていて、ものすごく彼女らしさがつまっている。特に踊りかたとか。
一緒にごはんを食べたときに、彼女がタイカ・ワイティティの『トゥー・カーズ、ワン・ナイト』(2003年/12分)を見せてくれたことを思い出す。
この短さ、シンプルな設定で、しっかり心つかまれる。すごい。そして彼女の映画もそうだ。
もっちー、あなたは未来のタイカ・ワイティティよ。こんな雑な褒め方だと、何も伝わらないね。
4月15日(水)
溝口健二『浪華悲歌』(1936年/71分)
パブリックドメインなので、YouTubeで観れます。たまに思い出す作品。
溝口は、女性をきちんと描けるというけれど。以下ネタバレあり。
劇中、主人公はかなり強気なのだから、最後は家族に全部打ち明け、ちゃぶ台ひっくり返してから家を出たっていいのではないか。
そんなことする気も起きないくらい、呆れたということなのか。
彼女の強い眼差しで映画は終わる。女性をおしとやか、聖母的に描かないという点で、女性をきちんと描いているようにも思うけれど。
最後に彼女があらゆることをぶちまけずに家を出て行くのは、我慢が美徳、みたいなものがあらわれていて。時代的にそういう展開になるのかもしれないけれど、それまでに描かれてきた彼女と乖離があるというか、設定がぶれてるような気がする。それだけ弱い立場であった、そういった諦めを描いたのだろうか。
あんなことやこんな辛いことがあったけれど、彼女は生きていく、みたいなのって、強さをかぶせてるだけで、描き方として優しくはない。
そのキャラクターの強さ、みたいなものに、甘えてる気がする。その設定に。
封建的な女性らしさからは女性を解放してるけれど、その主人公の強さって、彼女のなかの「男性的な強さ」に対してホモソーシャルで定義される「強さ」みたいなものに導く、手招きをしているだけなのではないか?と思ってしまった。
じゃあ、どう描けばよいのか、というのはわからないし、あの終わりでなければ、この映画は締まらないのだとは思うが。
1936年の溝口に求めすぎてるのかもしれないけど、そんなことを考えた。じゃあ、強さを描くってなんだろう…。
4月17日(金)
濱口竜介『天国はまだ遠い』(2016年/38分)
こちらも4月28日まで限定配信の作品。
濱口さんの映画は、浴びたいことばの(探していたことばの)シャワーを浴びているような気持ちになる。
今の自分にはそれ以上広げられないけれど、「時間というフレームの強固さ」ということばとかも。
ことば偏重なようで、映像でしかできないことをやってる。ミュージックビデオにならない。
不在。誰かのためではなく、自分のために映画は撮る。セラピー。時間。
「見えるもの/見えざるもの」というフレーズがよく濱口作品のキャッチになってる気がするけど、そういうことか。
男性の憑依の演技、難しかっただろうな。
最後の告白が、突然のことに思えないのがすごい。それだけ、この短い時間のなかで、ふたりのことをそれぞれを描いたということだから。
あ~、これと『虚空門GATE』を一緒に見たら、面白い気がする。また二本立て妄想。
やっぱり、映画は短ければ短いほど好きだ。
短くて、あっという間に感じる濃さを持っている作品が。
濱口監督の作品にふれたので、ミニシアターエイドに関連することを働く当事者として一言。
こんなときに、そんなことまで言えないのかもしれないが、ミニシアターが守られるだけでなく、
ミニシアターで働く人の生活も、きちんと守られなければ、それは文化を守れていることにはならないと思う。
誰かが無理をして、踏ん張りや疲弊によって成り立っている世界。根本的な仕組みから考え、見直し、できることがあるのかを、私は考えていきたい。