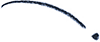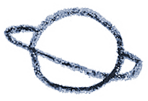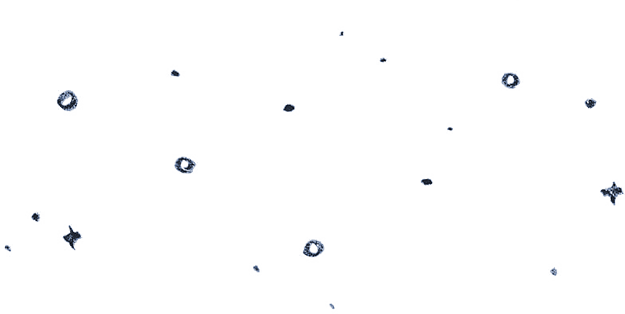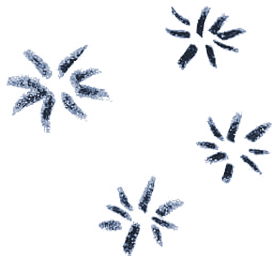文=パンフマン
第38回東京国際映画祭でアニメーション部門で上映されていたスペインの映画『デコラド』を観た。
2024年に日本で公開されたテディベアとユニコーンの戦争を描き、「可愛い×グロい」アニメとして話題となった『ユニコーン・ウォーズ』の記憶も新しいアルベルト・バスケスが監督を務めている。これが同監督の長編3作目にあたる。今作でも可愛らしい動物のキャラクターたちが辛い現実に直面しながら、もがき苦しむ姿を時にはグロい描写を交える作風は本作でも健在だ。
実写化だと生じるキツイ表現になるところを、二次元化で抑えられてはいるものの、可愛らしい動物やキャラクターが酷い目にあっているのを見るのはそれはそれで辛い気持ちにもなったりする。今回のテーマが現代に生きる人にとって一層身につまされる内容となっており、昔に流行った「ねこぢる」の漫画を連想したりもした。
ネズミのアーノルドは経済的、身体的、感情的、社会的な様々な要因から実存的な不安に陥ってしまう。タイトルの「Decorado」はスペイン語で舞台装置といった意味だが、劇中で度々繰り返される単語だ。アーノルドは失業に伴う無気力感、ミッドライフ・クライシス(中年の危機)などに苛まれながら生活する中で、現実感を失っていく。この世は作り物で映画のセットのように偽物の「舞台装置」なんだと感じ始める。辛すぎる人生がゆえに、この世界は嘘っぱちで誰かが作り出した中で踊らされているだけと現実感が消失していく「トゥルーマン・ショー」的な徴候を示してしまうのはごく自然なことだろう。監視してくる隣人、薬を処方する医師、没落した有名俳優など出会う人々が皆、巨大企業ALMA(アルマ)が共通して関わっていることに気がつき、その思いをますます強めていく。
私たちが暮らす世界は実は「ニセモノ」ではないかという問いを幾度となく投げかけてきたのは作家のフィリップ・K・ディックだが、彼の作品が今なお読まれ続けているのは絶えず共感を呼ぶからだろう。イギリスの批評家マーク・フィッシャーは現実への違和感の正体は資本主義ではないだろうかと「資本主義の終わりより、世界の終わりを想像する方がたやすい」との言葉を残している。資本主義で皆が幸せになれるはずと思われていたのにどうしてこんな世界になってしまったのか。
アーノルドには妻のマリアがいる。彼女はイラストやデザイン関係の仕事をしながら、何とか自我を保っているが、アーノルドの異常な態度に振り回されて、おかしくなってしまう。本作には動物以外に何故かキノコも登場するが、彼は子どもを育てるためにアーノルドに商品を買ってもらおうとするも、断られて、将来が見通せない。笑ったのは悪魔や幽霊も出てくるのだけど、降りかかったほんのちょっとした出来事をきっかけに悪魔でさえも落ち込んで鬱っぽくなるし、ゴーストとして彷徨いながらもまだ悩みが消えない様子で、ここは悪魔的な人物でさえも、幽霊になっても正気を保つのは難しい世界なのかと思わせる。というか大企業ALMA(スペイン語で魂の意味)側でさえもある種の病みを抱えていると明らかになる(この社屋がとても悪意のある形をしている)。
世界の真実とは何なのか。アーノルドとマリアの馴れ初めが回想シーンで流れる。彼らもかつては信念を持って、希望に満ちた生きていたと伝わるが、ふとした瞬間に歯車が狂ってしまう。それぞれ鬱的な要素を抱えながらも、友人が残した世界からの出口を示した地図を頼りに、抜け出そうと決意する2人(2匹?)。この世界は本当に「舞台装置」だったのか。ぜひ劇場で確かめてほしい。

作品情報
原題:Decorado
スタッフ
監督/脚本:アルベルト・バスケス
脚本:フランセスク・シャビエル・マヌエル
エグゼクティブ・プロデューサー:イバン・ミニャンブレス
エグゼクティブ・プロデューサー:チェロ・ロウレイロ
エグゼクティブ・プロデューサー:ホセ・マリア・フェルナンデス・デ・ベガ
エグゼクティブ・プロデューサー:ヌーノ・ベアト
作画監督:パメラ・ポルトロニエリ
キャスト
ダニエル・レマ・ブランコ
チェロ・ディアス・イソルナ
オスカル・フェルナンデス
95分/カラー/スペイン語・英語/日本語字幕/2025年 スペイン
予告編
長編の元となった11分の短編アニメ
妄想パンフ
A5タテ。登場キャラクター紹介、絵コンテとシナリオはスペイン語の勉強にもなるので、原語と一緒に記載してほしい。