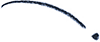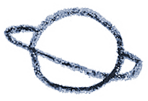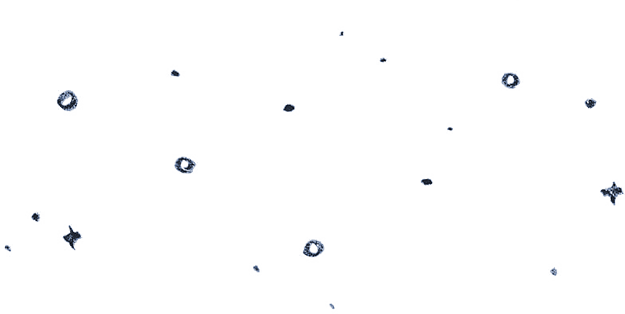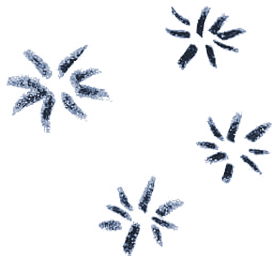文=パンフマン
第38回東京国際映画祭でウィメンズ・エンパワーメント部門で上映されていたエジプト映画『ハッピー・バースデイ』を観た。
エジプトにおける映画の歴史は実際に長くて、現在でも作品がそれなりに制作されているのだけれど、日本で観る機会はあまりないのが現状なのかもしれない。なので、本作はエジプトの現実の一端を知れる機会という意味で必見の一作だろう。
監督はニューヨーク・サウスブロンクスで生まれ育ったエジプト系アメリカ人サラ・ゴーヘルで、本作が初監督作となるが、トライベッカ映画祭で最優秀作品賞、脚本賞、ノラ・エフロン賞の3賞を受賞するなどデビュー作で数々の賞に輝いている。
ストーリーはカイロの裕福な家庭でメイドとして働いているトーハは雇い主の娘で仲良しのネリーの誕生日を一緒に祝うために、パーティーの準備を進めようとする…というもの(この物語ならばユース部門の作品にも当てはまりそうだ)。
トーハは主にネリーの祖母の世話を手伝っているのだけど、食事の準備だけではなく、倒れてきたら押し潰されそうなガスボンベやインシュリン注射などの薬品を取り扱ったりと結構ハードで責任のある役割も任されている。これは後々劇中で言及されるのだが、年齢的に違法な児童労働にあたると伺える。ところが、祖母は当然の扱いといった素振りを見せている。一方で、ネリーの母は多少後ろめたく思っている部分があるようで、これは世代による考え方の違いなのかもしれない。
ネリーを迎えに来るスクールバスが家の前に到着する場面では、トーハは運転手にネリーが遅れることを伝えるのだが、邪険に扱われてしまう。ここで思い出したのが、短編版が第97回アカデミー賞の一部門にノミネートされた山崎エマ監督『小学校~それは小さな社会~』(2024)に絡む中で知った日本の公立小学校とエジプトでの学校における関係。日本の公教育における特別活動がエジプトで国家プロジェクトとして導入され、エジプトの子どもたちや先生に良い影響をもたらしたという話題で、「学校に行きたい・好きになった」などと生徒の声が紹介され、集団の中で自分の役割を持ち、学校が安心して学べる場となり、自己肯定感が高まり日頃の態度が変わっていったというものなのだが、もとよりエジプトには学校に通えない・通わず働いている子供も一定数はいるのだろう。
そんな社会の有様をトーハの目を通して映し出していく。ネリーの母親とトーハが誕生パーティーに必要な食材を買いに街のショッピングに出かける場面では、トーハがアミューズメントパークやドレスショップでいつも以上にはしゃいでいる様子が見えてくる。どうもショッピングモールみたいな馴染み深い施設でも学校に通えない子にとっては、普段は立ち入れないような場所だとわかる。この流れで訪れた日本の某現代美術館にある「プール」のような水中に潜っている感じを味わえる場所で嬉々とした表情を浮かべるネリーがポスターに使われている。
そもそもトーハがネリーの家がある地区から出入りするにも、ゲートを通って持ち物検査が義務付けられているほどジェントリフィケーション化が進んでいたりする(『デオラド』でも住む地域による格差をディストピアとして描いていたが、こちらは本物だ)。ゲートから出たトーハが向き合うのは全く別の厳しい現実で、実家に帰ると母親と姉たちが川で魚を獲って、自分たちで売らなければならないという生活が待っている。
ネリーの誕生会に行きたい一心で、トーハは頑張って、魚を売り捌く。パーティーに間に合うのか。近所の親切な男の子がトゥクトゥクに乗せて、ネリーの家まで送り届けてくれるが…。普段の日常ではなく、お祝いの場で突きつけられる現実ほど残酷なものはない。

作品情報
原題:Happy Birthday
スタッフ
監督/脚本:サラ・ゴーヘル
エグゼクティブ・プロデューサー/脚本:モハメド・ディアブ
プロデューサー:アフマド・エル・デスーキー
プロデューサー:アフマド・バダウィー
プロデューサー:アフマド・アッバース
共同プロデューサー:ジェイミー・フォックス
共同プロデューサー:ダタリ・ターナー
キャスト
ネリー・カリム
ハナン・モタウィ
ドーハ・ラマダン
91分/カラー/アラビア語/英語、日本語字幕/2025年/エジプト
妄想パンフ
エンドロール前に映し出される家族写真の意味を語る監督インタビューの他、エジプト映画のパンフ自体が珍しいので、現代エジプト映画の状況を紹介したりする。出演者や共同プロデューサーを務めたジェイミー・フォックスへのインタビューなど。A5サイズ。