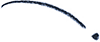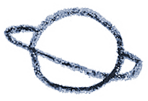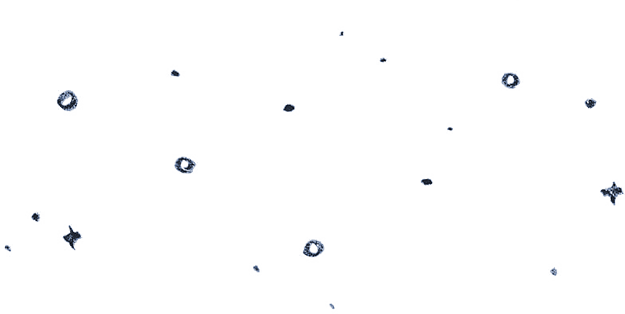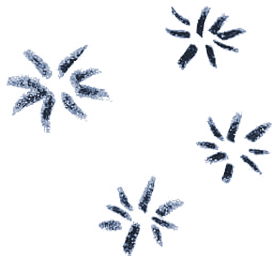文=小島ともみ
カヤ・トーストをご存じだろうか。
こんがり焼いた薄切りトーストに、ココナッツとパンダンの葉の香りを閉じ込めた緑色のジャム、そして薄いバターを挟んだもの。それを、半熟卵と、ロブスタ種を主体にした練乳入りの甘く濃い「コピ」で流し込む。立ちのぼる湯気とともに。シンガポールの伝統的な朝の光景だ。そのカヤ・トーストが食べられる「コピティアム(伝統的なコーヒー店)」は、さまざまな言語や文化背景を持つ人々が同じテーブルを囲み、世代と世代が日常の会話でつながる「広場」そのものである。
シンガポール独立60周年(SG60)を前に制作された本作『コピティアムの日々』は、このコピティアムという広場を中核に据えた6編のオムニバス映画だ。独立50周年の『7 Letters』の系譜に連なるこの企画で、6人の監督が日常の「場(コピティアム)」を繊細な通路として、そこに生きる人々の「言語」「記憶」、そして「ケア(気遣い)」の実践を、丁寧に縫い合わせていく。全編を貫くのは、「コーヒーを淹れる」「客が待つ」「店主が客に呼びかける」といった、ごくありふれた飲食のしぐさだ。しかしこの反復こそが、ささやかな喪失と、思いがけない再接続のドラマを具体化していく。
映画は意表を突く武侠ラブコメで幕を開ける。“コーヒー店の娘”を神話化するような突飛な様式だが、これは締めのエピソード「モーニングコール」へとつながるしなやかな糸の始まりでもある。素人歌劇団の悲喜こもごもを描く一編では、未経験の恋を演じきれずに葛藤する中年女優の姿が印象的だ。“演じること”が、現実の他者との関係を修復するという逆説。都市開発によって消えた幻影としてのコピティアムが、劇団を支えてきたスポンサー夫婦と女優のあいだに流れる言葉にしがたい感情を、優しく包み込む。
本作のなかで静かに重い錨を下ろすのが、1986年の「ホテル・ニューワールド」倒壊事故をめぐる追悼譚である。映画は、事故前夜に宗教の差を越えて一夜を共にした男女の記憶を、抑制の効いた筆致で描く。翌朝の突然の崩落。33名の命が失われたこの都市災害の記憶は、コピティアムの喧騒の中に静かに沈殿し、個人の物語と都市の傷跡を重ね合わせる。
また記憶は、音となって蘇る。ディアスポラのサウンド・アーティストが登場する一編では、湿った床を擦るサンダル、皿の触れ合い、人々の会話のノイズ――それらコピティアムの「音」を採集し、ミックスする過程が追われる。聴覚によって故郷を再構築する試み。彼女にとって、コピティアムは視覚ではなく音響として存在している。
そうして紡がれてきた全編をやわらかく束ねるのが、終章の「モーニングコール」である。携帯電話を嫌う祖父と孫が、祖母の忘れ形見の固定電話を探して市内を巡るロードムービー的な掌編。電話は巡り巡ってアート作品としてコピティアムに帰還し、かつて人々を繋いだ「呼び出し声」そのものが“展示”される。祖父が話す海南語、親世代が使うシングリッシュ、そして孫世代が操る流暢な英語。その語感のズレが生む、おかしくも拭いきれない距離感を埋めるのもまた、コピティアムである。頑固だった祖父は地図アプリに目を丸くし、亡き祖母の口調を娘である母がまねて父のスマートフォンの着信音としてしのばせる。「記憶の継承」がささやかな生活音にのって行われる軽やかさ。
作風の振幅が大きいにもかかわらず、本作が不思議と散漫にならないのは、ひとえに「コピティアム」という現実の場が、すべての物語の確かな重力として機能しているからだ。そして、“食べる/飲む”という日常の動詞が、過剰な説明を抜きに全編を豊かなハーモニーとして響かせている。もちろん、エピソード間の急激なトーンの変化に戸惑う瞬間がないわけではない。だがそれすらも、最終章の静かな円環によって、見事に収束されていく。テーブルに置かれたカップから立つ湯気は、一瞬で消える。しかしその甘い香りは、記憶の随所に染む。本作は、その“残り香”としての日常を、その儚さと確かさを、静かに讃える映画である。SG60の節目に、なんと豊かで誠実な祝祭だろうか。
【コピティアムとは?】
「コピティアム(Kopitiam)」は、マレー語の「コピ(Kopi=コーヒー)」と、福建語・客家語の「ティアム(Tiam=店)」を組み合わせた造語。主にシンガポールやマレーシアで見られる、伝統的なコーヒーショップを指す。多くの場合、ドリンクスタンド(コピを淹れる店)が中心となり、その周囲に様々な料理(麺類、ご飯もの、点心など)のストール(屋台)が併設されたフードコート形式をとる。定番の朝食は、カヤ・トーストと、温泉卵より少し緩い半熟卵(醤油と胡椒をかけてかき混ぜる)、そして甘い「コピ」のセット。人種や言語、所得に関わらず、誰もが日常的に集う地域の交流拠点(ハブ)として、社会的に重要な役割を担っている。
【ホテル・ニューワールド崩壊事故】
1986年3月15日、シンガポールのリトル・インディア地区にあった6階建ての「ホテル・ニューワールド(新世界酒店)」が、前触れなく突如として崩壊した事故。建物にはホテル(リアン・アパートホテル)のほか、銀行の支店やナイトクラブなども入居しており、最終的に50名が瓦礫の下敷きとなり、うち33名が死亡する大惨事となった。事故調査の結果、建物の構造設計段階での計算ミス(建物の自重=死荷重しか考慮されておらず、家具や人、設備の重さ=活荷重が計算に入っていなかった)が原因であると結論づけられた。本作は、このシンガポール国民の記憶に残る悲劇を、一つのエピソードの背景として扱っている。

作品情報
原題:Kopitiam Days
スタッフ
監督:ヨー・シュウホァ
監督:ショキ・リン
監督:M・ライハン・ハリム
監督:タン・スーヨウ
監督:ドン・アラヴィンド
監督:ワン・グォシン
エグゼクティブ・プロデューサー:エリック・クー
エグゼクティブ・プロデューサー:フラン・ボルジア
エグゼクティブ・プロデューサー:リム・テック
キャスト
リッチー・コー、ホン・フイファン、ザヒラ・ハミド、アイリス・リー、スティーブン・ゼカリヤ、ヤン・シービン
129分/カラー/英語、北京語、マレー語、タミル語、中国語方言/英語、日本語字幕/2025年/シンガポール
妄想パンフ
都市の記憶を綴るアルバム風パンフレットに。劇中にあらわれる、多様な文化に支えられるシンガポールの日常場面をできるだけたくさんおさめる。カヤ・トーストのレシピはマスト。