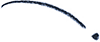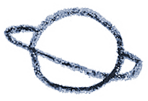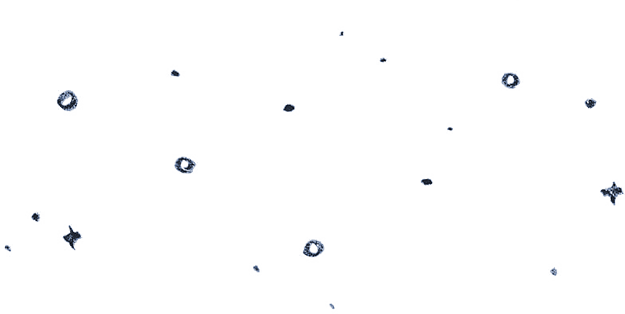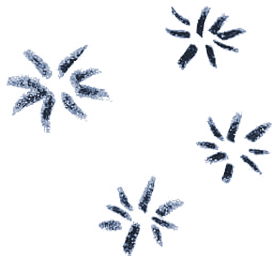文=屋代忠重
「空を自由にとびたいな」人類が長い歴史の中で抱き続けてきた“大それた夢”は、1783年にフランスのモンゴルフィエ兄弟が、人類初の熱気球飛行に成功したことにより現実のものとなった。さらに1903年にアメリカでライト兄弟が初の動力飛行に成功し、飛行機が空想から現実の乗り物として歴史に登場した。しかし『飛行家』の主人公ミンチーはそこで満足する男ではなかった。平凡な労働者である彼は自作の飛行装置で空を駆ける情熱に燃えていた。しかしある事件からその夢をあきらめ、妻のヤーフェンと廃工場を改装してダンスホールを経営するようになる。中国社会に押し寄せる時代の変化に揉まれながら日々を生きるミンチーだったが、空を駆ける夢が再燃する出来事が起きる。2017年に出版されたシュアン・シュエタオの短編集「飞行家」。監督/脚本は『再会の奈良』(21)のポンフェイ。原作者のシュアン・シュエタオはポンフェイと共同脚本を務め、エグゼクティブ・プロデューサーにもクレジットされている。予備知識なしで観れば直球ど真ん中の、笑って泣けるエンタメ作品なのだが、他にもうひとつ別の一面を持っている。いま中国でムーブメントとなっている「東北ルネッサンス(东北文艺复兴)」だ。
作品の主な舞台となっているのは1970年代~90年代の中国東北部(主に遼寧省、吉林省、黒竜江省の東北三省)。1930年代から中国の工業の中心地として繁栄しており、国営工場の労働者たちは“鉄飯椀”と呼ばれる終身雇用まで保証されていた。労働者向けに国営の巨大な複合施設が建設され、労働人民文化宮と呼ばれるそこには映画館や図書館、大小さまざまなホールがあり、労働者たちの交流などに使われた。ミンチーがダンスホールを開業するために借りた隕石博物館もその流れでつくられたのだろう。しかし鄧小平が70年代後半から改革開放を打ち出した結果、80年代頃から産業のパラダイムシフトが起き、東北部の衰退が徐々に始まる。さらに90年代に入り市場開放をおこなった結果、国営企業と民間企業のパワーバランスが完全に逆転。国営の工場は次々と閉鎖され、“鉄飯椀”だった労働者たちも一斉に解雇。東北部だけで数百万人の失業者が溢れかえった。工場や労働者向けの複合施設は廃墟と化し、かつて繁栄していた東北部は中国のラストベルトとなり、完全に時代から取り残されてしまった。その様子はワン・ビンの『鉄西区』(03)で描かれているとおりだ。だが2010年代後半から遼寧省出身で、本作の原作者でもあるシュアン・シュエタオの「平原のモーゼ」(16)など、東北部を舞台とした小説が注目を浴びるようになる。決定的なのは、吉林省出身で本作にも出演しているドン・バオシー(GEM)が19年に発表した「野狼DISCO」の大ヒットだ。その時のインタビューで生まれた言葉が「東北ルネッサンス」である。ミンチーの妻、ヤーフェン役として出演しているリー・シュエチンも、遼寧省出身のスタンダップコメディアンとして、このムーブメントの最前線で活躍している。20年代に中国経済の停滞が始まり、人々はその不安を東北の衰退に重ね合わせ、出身である東北部への複雑な感情、労働者階級の人々が、衰退する街の中で前を向いて生きていく姿を表現する東北ルネッサンスは多くの人を共感をえるムーブメントとなった。
映画終盤、ミンチーは一度は捨てた空を飛ぶ夢に向き合うのだが、その時点で最早ただの発明家、夢みる変人、よき労働者以上の存在になっている。もう一度飛ぶ決断をしたミンチーに対して皆が協力的なのは、もうどこに行くこともできず、呪いのように土地に縛り付けられた東北の人々の希望だからだ。ミンチーが空を飛ぶということが、人々にとって自由であり解放の象徴なのだ。その解放感を表すように飛行シーンはたっぷりファンタジーとして描かれている。重い現実という滑走路と、空を飛ぶファンタジーの絶妙なバランスが。たとえ血を流し倒れても、己の力で立ち上がるミンチー。そんな彼の半生を描いたこの映画は、人間讃歌であり東北の人々の不屈の魂の物語だ。

作品情報
原題:Take Off[飞行家]
監督/脚本:ポンフェイ
キャスト:ジャン・チーミン/リー・シュエチン/ドン・バオシー/ジャン・ウー/ドン・ズージェン
118分/カラー/北京語/英語、日本語字幕/2025年/中国
妄想パンフ
A4タテ。人類の空への挑戦の歴史をまとめたページや、ミンチーの飛行装置を特集した記事など科学図鑑みたいな内容。