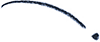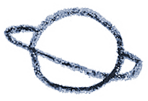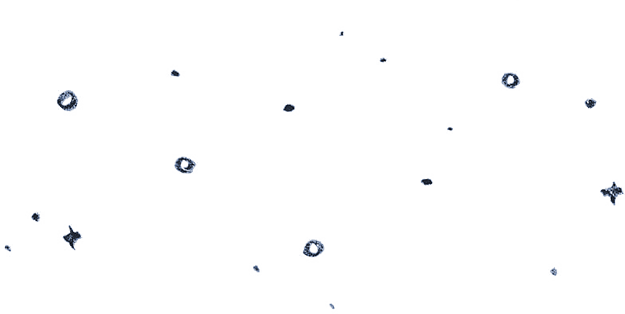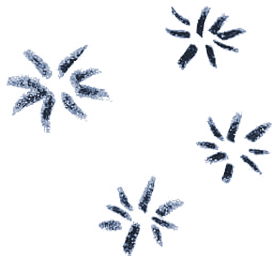文=屋代忠重
旅の始まりはいつだって痛みから始まる。チャン・リュル監督の映画はいつだってそうだ。
そして彼の映画は全て平熱36.5℃の体温だ。痛みも苦しみもまるで嘘のように平静で、激痛や高熱でうなされない。ただ無表情に疼痛を街にあずける。ときに説明できない不安や喪失感の正体を探しに今いる場所から飛び出して、それを教えてくれるかのように街の姿を映し出す。決して答えが見つかるとは限らない。ただ行かなければいけない気がする。そんな衝動一つをかばんに詰めて、彼の映画は幕を開ける。
本作『春の木』は、チャン・リュル監督が成都の峨眉(アーメイ)撮影所を訪れた際に、再開発のため撮影所が取り壊されることを知り、急遽ここを舞台にして映画を撮ることを決めたそうだ。時間や予算などの制約があるなか、即興性を重視した実験的な演出をまじえ、消えゆく撮影所の面影を切り取りつつ華やかな都市に変貌していく成都の対比を映し出していく。故郷の成都を離れてる間に地元の方言を忘れてしまい、掴みかけた大きなチャンスを失った俳優の春樹(チュンシュー)。大きな挫折を味わった彼女は、故郷の成都に戻り立ち直ろうとする。成都に着いた彼女は峨眉撮影所のすぐ隣に部屋を借り、連れてきた愛猫と暮らし始める。かつて自分に演技を教えてくれた張梅(ジャンメイ)のもとを訪れた春樹は、張梅の息子の冬冬(トントン)と出会う。
ここからの物語は散文的で、とりとめのないスケッチを観てるような感覚で進む。監督インタビューによると、本作の撮影自体が急に決まったこともあり、脚本も最低限の分だけ用意して、俳優たちと話し合いながら、台詞や動きなどを決めて撮影を進めていったとのこと。その結果、標準語、成都方言、上海語、フランス語、はては無言まで、さまざまな言葉が飛び交い、まるでホン・サンスの映画のように、会話が微妙にかみ合わないディスコミュニケーション感を生み出している。ある種のオフビート感と可笑しさを醸し出している。そして英題の『Mothertongue』(母語)の通り、全員が飾らず遠慮なく各々の母語を話すなか、それを忘れてしまった春樹の挫折が次第に浮き彫りになっていく。こういった多言語が混ざりあう感覚は、日中韓を舞台に映画を撮り続けるチャン・リュル監督ならではだろう。そして感情の起伏をほとんど出さず、無表情なほどに雄弁になる俳優陣の演技が相乗効果を与えている。特に複雑な人間性をもつ張梅を演じるリウ・ダンが白眉。静寂に包まれた撮影所の光と影の隙間をさすらう彼女の動きは、まるで能の動きのようだと感じていたら、リウ自身2013年に来日して能楽「羽衣」で主演をつとめ、日本で能を演じた最初の中国人とのこと(そう言われると、あの長寿体操もそれっぽく見えてくるから不思議)。冬冬を演じるワン・チュアンジュンも、母語である上海語を披露したり、あれだけ無表情を貫いていたバイ・バイホーが、あるシーンで突如満面の笑みで踊り出したり、出演者たちのもてるスキルを惜しみなく出して全員一丸となって芸達者ぶりを披露している。
少し目を離すとどこかへ飛んで行ってしまうような、とにかく繊細なエピソード群をまとめるチャン・リュル監督の手腕は見事。特に登場人物たちが峨眉撮影所をあてもなく漂う様子は、まるで監督自身が消えゆく撮影所をいつまでも名残惜しんでいるかのよう。もしかすると、これはこれから実際に自身にやってくる喪失感を受け止めるための映画だったのではないか。監督だけではない。私たち自身も無意識のうちに春樹のように何かを失い、残ったものを探しながら街で暮らしている。春樹にとっての失ったものと残ったものを自分たちと重ね合わせるがゆえに、このまま終わらないで欲しいとさえ思う。撮影所は解体されてなくなる。しかし今ある街の姿も変容していく。その変化の連続性をずっと観ていたい。そんな気にさせてくれる。もちろんこの映画の主人公は春樹(チュンシュー)だ。しかし衝動をかばんに詰めこんで、この映画を撮る旅にでたチャン・リュル監督自身、そして観ている私たちも主人公。いまではそう思えてくる。

作品情報
原題:Mothertongue[春树]
監督:チャン・リュル
キャスト:バイ・バイホー/ワン・チュアンジュン/リウ・ダン/ポン・ジン
122分/カラー/北京語/英語、日本語字幕/2025年/中国
予告編はこちら
妄想パンフ
A5タテ。峨眉撮影所の面影を残すアルバムのような内容に。