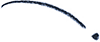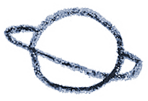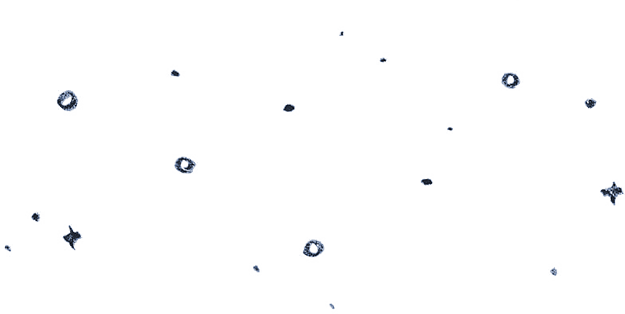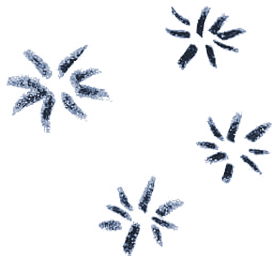文=小島ともみ
式を控えた花婿が不安げに車を走らせる。花嫁からの電話には上の空で応え、何かを探してあたりを見回し、明らかに追い詰められた表情でハンドルを握る。しかしどうやら行き過ぎたらしい。慌ててバックで道を戻り始めた瞬間、衝撃と共に車のリアガラスが大破し、道路に血だらけの女性が現れる。彼が轢いたのではない。女性は、上から降ってきたのだ。
冒頭から異様に張りつめた空気で始まるイラン映画『マリア』は、28歳の監督メヘディ・アスガリ・アズガディのデビュー作である。その鮮やかな手腕も、イランでは著名な映画教師であり、自ら映画学校を運営、テレビ映画や番組の脚本を書き、監督も務める華々しい経歴の持ち主と知ると納得がいく。そんな監督が送りだした本作は、イランの閉鎖的な地域性と、映画産業のからくりに翻弄されて失踪した女性をめぐる社会派ミステリーである。
ファルハドは、妻で女優のパリサの両親が経営する映画制作会社で監督をしている。会社まわりも家族の事柄も、決定権は義父のペイマンではなく義母のゾーレが握る。ゾーレは婿であるファルハドにも遠慮がなく、そんな母に似たパリサも物腰が強い。会社にはヒッチコックの『裏窓』や、トリュフォーの『アメリカの夜』、アントニオーニの『欲望』など、イランでは検閲の対象になりそうな表現を含む欧米の映画ポスターがずらりと並ぶ。イスラム法により、女性は結婚すると人権が一層低くなるといわれる男尊女卑社会のイランにあって、ゾーレもパリサもそれなりに自由があり、一家は極めて開かれているように見える。その一方で、転落した女性、マリアの家族や属するコミュニティは厳格なルールに従って暮らしている。
イランには、目には目を実践する「キサース」と呼ばれる同害報復刑が存在する。国際社会の批判を浴びながら、石打による死刑、失明や四肢切断といった身体を損傷させる刑罰が今もなお実施されている。もちろんこれらは刑執行局の行う公的刑罰だが、この理は一部民衆のなかに深く根づいているのだろう。劇中でも両親を亡くしたマリアの面倒をみる祖父が時折こうした思想を匂わせる言葉を口にする。彼はまじないで病を治す呪術医で、車の弁償をめぐって彼の家を訪ねたファルハド一行は、その術式の真っ最中に遭遇して大いに戸惑う。革命後、紆余曲折を経て、識字率の上昇や大学進学率の増加など、徐々に近代化が進んできたイラン社会だが、イスラム教の価値観をそこにどう融和させていくかには濃淡があり、それによって生じる社会階層の差が物語の根底にある。
この祖父との交渉をきっかけに、実はファルハドはマリアとは面識があったことが明らかになり、一家は地域社会の闇に巻き込まれていく。ペイマンと一緒に進めていた企画で、後にパリサを主演に公開した作品は、元々マリアが主役を務めるはずであった。テスト撮影で撮った、マリアの演じる娼婦が車を呼びとめて客引きをする映像がネットに流出。本物だと思い込んだ者たちの誹謗中傷にさらされて、マリアは表を出歩けなくなってしまい、やむを得ず姿を消したのだった。いわゆるハリウッド映画のサスペンスのような目まぐるしい展開はない。しかしマリアの転落が事故なのか事件なのかをめぐって証言者たちが警察で鉢合わせし、耳打ちで情報が伝わる様子は、ネット炎上とは違う現実社会の恐ろしさを感じる。無自覚な加担者により一瞬で広まるネットの情報は、日々の更新で色あせるのも早いが、狭い地域で共有された情報は必要なところへ確実に届き、容易には忘れ去られない。映画の終盤、物語の焦点は、マリアの失踪は自らの意思か、噂の広まりを恥じた家族による監禁だったのかに移行する。誰のどの言葉を信じるか、あるいは信じたいかで見え方は180度変わり、判断は観る者の解釈に委ねられる。劇中でたびたび姿を見せるマリアは、赤い民族衣装のシルエットのみで顔は分からない。マリアは誰でもなく、また、誰でもあり得る。その顔がはっきり映る場面が映画の終わりにやって来るが、それこそが何よりも強いメッセージになっている。
表現の自由が保障されていない国での映画制作は、時に危険を伴う。同じく本映画祭で上映された『タタミ』で共同監督を務めたザラ・アミール・エブラヒミは、私的なセックステープの流出スキャンダルの被害者となり、俳優として成功をおさめていたイランからフランスへ亡命せざるを得なくなった。被害者側がいわば社会的制裁を受け、全てを失う状況は本作のマリアの姿とも重なる。その『タタミ』は、イランの女子柔道をめぐり裏側でうごめく政治の思惑を生々しく描いた作品だ。撮影は秘密裏の内にジョージアで行われ、当然ながらイランでは上映禁止である。『マリア』には直接何かを問うような描写はみられないが、女性が女性というだけで選択の自由がない人生を歩まざるを得ない痛ましさはにじみ出ている。今年に入って14回以上ネット規制が行われているイランでは、政府の目をかいくぐって情報を得ようとする市民の努力がIT能力を向上させたといわれている。キアロスタミが「子どもの話ならよい」と当局の検閲をかわして『友だちのうちはどこ?』をつくりあげたように、表現者も自分の主張をストレートにぶつけるのではなく、工夫を凝らして練り込まなければならないのが、イランの映画制作の現状なのだろう。しかしその丁々発止から生まれた表現が、作品をより鋭利にし、社会の矛盾をえぐる力になる。それがイラン映画を面白くしているひとつの要因ではないだろうか。
36TIFF 2023/10/27

作品情報
原題:Maria
監督:メヘディ・アスガリ・アズガディ
キャスト:カミャブ・ゲランマイェー、パンテア・パナヒハ、サベル・アバール
97分/カラー/ペルシャ語/日本語・英語字幕/2023年/イラン
予告編はこちら
妄想パンフ
アメリカのレターサイズ (8.5 x 11 インチ) を使用、3 穴パンチ紙に片面印刷。劇中で何度か現れるマリアの赤い民族衣装、花売りの少年の花、血のついた赤いシャツなど、重要アイテムをところどころ本文の裏面印刷で入れる。本作がデビュー作というアズガディ監督にはロングインタビューを。作品について余すところなく語ってほしい。イラン映画の概説や考察を専門家の視点から解くレビューをぜひ。