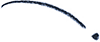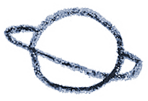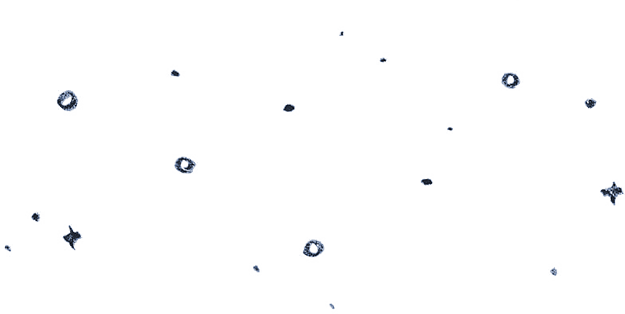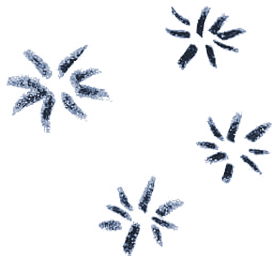文=小島ともみ
毒蛇や害虫を食べてしまう孔雀は、その生命力の強さから邪気を払うものとして信仰されてきた。繁殖力も強いため、子孫繁栄の意味も持っている。仏教ではインドの女神マハーユーリーに由来する孔雀明王が人を毒する煩悩をなくし安寧をもたらす神として崇められている。「明王」と名の付く神は、不動明王をはじめとして憤怒の表情を浮かべているが、孔雀明王だけは例外で、優しく穏やかな顔立ちをしている。国民の多くが仏教徒だというスリランカの映画である本作のタイトルも、そんな孔雀のイメージとは無縁ではないだろう。慈悲深くも衆目を救う女神の顔を曇らせるものとはいったい何なのか。
青年アミラが乳飲み子と幼いきょうだいを引き連れ、ほぼ身ひとつでコロンボにやって来たのには理由がある。重い心臓病を患う妹に治療を受けさせるためであった。両親は既になく、他に頼れる親族もいない。アミラたちは廃ビルの屋上を仮の住まいとして妹の治療費の工面に奔走するが、なかなかうまくいかない。そんなとき、アミラは裕福そうな女性に声を掛けられ、彼女の下で働くことになる。マダムと呼ばれる彼女は望まない妊娠をしてしまった女たちを屋敷に留め置いて出産させ、生まれた赤子を外国人に斡旋する非合法のブローカーであった。目の前には赤子を手放すときに嘆き悲しむ女たちの姿、病院のベッドの上にはさまざまな機械を取り付けられて苦しむ妹の姿。アミラは罪悪感と使命感にさいなまれながら、流されるままにマダムの屋敷で働き続ける。
昨今の妊娠と中絶をめぐる議論は、当事者たる女性主導というよりも、プリミティヴな善悪の価値観や、倫理や秩序を楯にした外からの押しつけで進んでいるように感じてしまうときがある。「産まない」選択の一手段として「中絶」を選ぶことは、本来は非常に個人的な行為であるが、たしかに米国では国を揺るがす大きな争点になるなど、一国の政治を左右し、さらには国際的な対立を招きかねない極めて公的な問題になっているのは間違いない。本作が描くのは、そこへもってさらに妊娠を商売の道具する者たちの介入である。貧困や劣悪な家庭環境などから生じた望まない妊娠を終わらせたい女たちに救いの手を差し伸べ、逆に子を望みながら恵まれないカップルに赤子を授ける。仲介業者もそれなりの斡旋料を手にする。一見、三方よしの関係にみえて、当然のことながら産む女性の身体にかかる負担や命のリスク、売る側・買う側の経済格差などが絡み合い、決して公平にはなり得ない。映画はその暗部を分かりやすい構図でみせてくれる。
映画のなかで一つキーになるのが「カルマ」という考え方だ。過去の行為は良くも悪くもいずれ自分に返ってくるという仏教の思想である。望まない妊娠をした娘に堕胎を許さない親は、ある意味で命を奪うという行為が娘にはね返ることを恐れ、現世で何もしないまま死んでいく孫たる胎児の来世を案じたのかもしれない。マダムの選択もこのカルマを思えば腑に落ちる部分はある。
プシュパクマーラ監督は11歳で父を亡くし、長男として母と二人、家族の世話をしてきたという。アミラがみせる戸惑いや焦燥は監督自身の経験が反映されているのだろう。女性の権利をどう考えるかといった点にまでは踏み込んでいないものの、闇の内部を男性の目でえぐる本作は、女性の身体の道具化という問題を浮き彫りにする。自分の身体のことは自分で決める。女性は時として、そんな極めて当たり前の選択ができない不利な立場に置かれがちであることを、あらためて考えさせられる作品である。
35thTIFF 2022/10/26

作品情報
監督:サンジーワ・プシュパクマーラ
キャスト:アカランカ・プラバシュワーラ、サビータ・ペレラ、ディナラ・プンチヘワ
103分/カラー/シンハラ語 英語・日本語字幕/2022年/スリランカ、イタリア
予告編はこちら
妄想パンフ
B5横。上記ビジュアルを使用。真ん中に赤い文字で「孔雀の嘆き」とタイトルを入れる。
生殖ビジネスや代理母出産の問題点についての論考を、専門家の視点から展開。