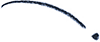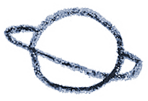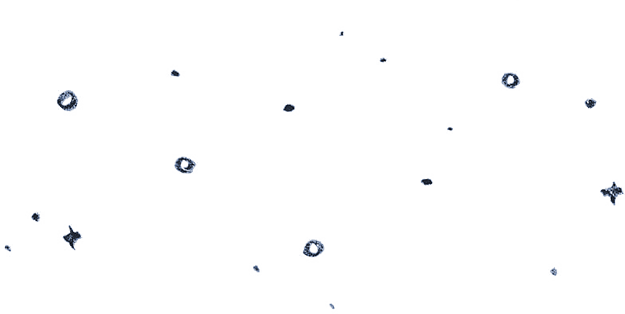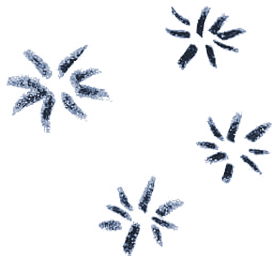文=竹美
『ザ・クラフト』(1996年)は、90年代という超自然ホラー不遇の時代に製作された魔術ホラーの佳作。うだつの上がらない女子高校生グループが黒魔術に出会う。魔力を開花させていく彼女たちに我々も同一化し、気分が高揚するも、彼女たちは私利私欲に走って悪事を働いたため、罰として魔力を封じられてしまう。面白い一方で浮かばれない話である。
今回取り上げる映画『ザ・クラフト レガシー』は、『ザ・クラフト』の続編。製作したブラムハウスは、2010年代以降に起きた価値観の素早い変化を巧みにホラー映画に織り込み、新時代を演出してきた。今回は、本作の何が「レガシー」で、何が新しくなっているか考えてみたい。
前作と同じく、魔術に凝っていた三人の女子高校生の前に転校生が現れる。彼女の出現により彼女たちの魔力が完成し、若い魔女集団が誕生…ここまでは同じだが、今回は結束の輪を完成させた彼女たちが「悪」を倒す形になっている。セーラームーンはじめ魔法少女もの、または戦隊ものを思わせる中二感が満載でうれしはずかしな一方、そのように描くことで「魔女」から「悪いもの」が脱色されている。
本作と前作を比較してみて、削除された最も大きな要素は「女の子の仲違い」である。前作で悪役になった魔女たち、その中でも特にファルーザ・バークの三白眼とビッチ演技は痛快だった。彼女は『オズの魔法使い』のディズニーによる続編『リターン・トゥ・オズ』でドロシーを演じた人なのだが、同作のお姫様であるオズマ姫よりも性悪のモンビ王女が気になった私としてはファルーザの不敵な顔はうれしい。が、同時にそれは彼女のキャラクターが本来悪意を持っているという印象を残す。今回の続編では、魔女を脱色して悪から切り離した上で、より強力な「モンスター=悪」を登場させた。2020年代の今、ハリウッド映画における「悪」とは、男性性をコントロールできない男である。
『ブローク・バック・マウンテン』(2005年)は、今なら、二人の男性同性愛者が、愛と社会の抑圧ゆえにそれぞれの妻や家族に対して行った仕打ちにもフォーカスするだろう。メキシコのホラー映画『触手』(2016年)からオスカー候補作『パワー・オブ・ザ・ドッグ』(2021年)まで、男性同性愛者は被差別者としてのみ描かれなくなってきた。彼ら自身が男性性の暴走を抑え込めない限り、罰として「処罰(=殺害)」される。一時期、映画の中の同性愛者は死ぬ運命にある病人や犯罪者の役ばかりだと批判されていた記憶があるのだが、再び条件付きで処罰されるようになった。男性同性愛者は「普通」の仲間入りをしたことで、同時に男性として裁かれる立場に立っている。『サムワン・インサイド』(2021年)ではゲイのアメフト部員が登場し、冒頭で結構な目に遭わされるのだが、暴力行為に理解を示す「男子」枠に収まっていたのは非常に新鮮だった。
ブラムハウスは、『透明人間』で、男性性をベースにした支配欲を悪として抽出し、リー・ワネル監督に「処罰」を任せた。『ザ・スイッチ』(2020年)では男女の中身を取り換えることで、男性の暴力と若い女性のアクション演技を捻った形で見せつけた。したがって『ザ・クラフト レガシー』が男性に大いに問題があると描くのもその流れの上にあると見える。例えば、転校してきた少女リリーが初日の教室である事故に遭うが、それをある男子がひどくからかう。トイレに逃げ込み泣いていたリリーを救うのが三人の魔女候補たちだ。仲良くなった4人は、復讐としてその男子に魔法をかける。すると彼は「Woke」してしまう。この語は「意識が高い人になる」とでも訳せばいいのだろうか。彼は男性的な攻撃性をすっかり失う。ここが非常に面白い。「悪いもの」を自分から切り離したと言うべきか。彼は、率直に謝罪ができるようになり、女の子たちにも仲間として受け入れられる。のみならず、彼の中で抑圧されていた色々な願望を告白するまでになる。登場シーンでは「即死して?」と思わせた嫌な男子が、魔法で図らずも思想転向した結果、自ら心地よく生きられるようになり、攻撃性が消えると演出した。実際のところ、人間の心理とはそうなのだろうか。悪い部分を切り離したら、自分も周囲も幸福度が増すのだろうか。そうだったらいいと思うのだが、本作は彼についての描写を直ぐに止めてしまう。
ところで、暴力的な警官が悪魔祓いの世界に入っていく映画『NY心霊捜査官』(2014年)の原作『エクソシスト・コップ』(ラルフ・サーキ著、2001年)を読むと、90年代に悪魔崇拝にのめり込む若者の存在を懸念する記述が出てくる。曰く「大部分の学校では、白魔術であれ、黒魔術であれ、魔術を行う自称魔女が、生徒の中に少なくとも二、三人はいる」として、「不満をかかえた」若者が悪魔に引き寄せられているとのこと。著者にとっては、第一作の『ザ・クラフト』で示唆されたような、学校にも家にも居場所がない子たちが魔術の真似事をして気晴らしをしているのかもしれないという視点は必要ない。その現象は悪がはびこる兆しであり、打倒すべき状況だと思っているのだから。なお「悪が蔓延っている」世界だからこそ、筆者は自己の暴力性に向き合う必要がないのかもしれない。悪魔祓いという形で彼は自己の暴力性の使い道を見出したのかもしれない。今のブラムハウス社なら彼をどんな風に描くだろうか。
「悪魔」は、『ザ・ウィッチ』や『へレディタリー 継承』では、人格の抑圧や「ノーマル」な家庭からの脱出口として捉えられ、救いの意味を与えているようにも読めるが、そう明言はしていない。米映画では、悪魔は基本的に「悪」なのだ。一方、本作は魔術と悪魔の関係を描かず、善のパワーに書き換えた。これはどういう意味なのだろう。
最近気に入っている映画批評家のロビン・ウッドは、伝統的なホラー映画は、「異常」(モンスター)が「正常(=ノーマル)であること」を脅かす様を描いてきたと考えていた。その観点から言うと、本作はじめ、社会的な価値観の変動(或いは動揺)を織り込んだ最近の米国のソーシャルスリラー作品では、「異常」と「正常」の内容はともかく、線引きの感覚自体は維持されている。また、本来のホラー映画のような形で「異常」をシンボリックに見せる程度ではなく、実在するものを「異常」として描き出し、「正常」が異常な「あいつら」に対し正義の裁きを下すかのように見える。本作の魔女は「正常」側にいる。観客は、悪役の「モンスター性」が自分の「外」にあると確認しなければならないのかもしれない。「正常」の側にいる魔女に共感して初めて、本作が体現する「正常」の範囲に自分がいることを確認できる。一方、この場合の「正常」とは「誰の」普通なのだろうか。
ソーシャルスリラーは、悪役のモンスター性と実在する属性(性別、ジェンダー、人種等)を明確に結びつけることで、「正常」空間を演出する。しかし、モンスター側の属性をいくつか持っている観客(白人でシスジェンダーで異性愛者男性)にとっては踏み絵になっているのではあるまいか。自分の身体や欲望からは逃げられないから。『サムワン・インサイド』を観ると、米国の若い層は、自分がこの新しい「正常」に入れるのかと緊張していることが感じられる。大ヒットした『死霊館』シリーズは、「異常」とモノガミーの核家族という「正常」な愛のシンボルが激突する古式ゆかしい物語である。ソーシャルスリラー的なものに慣れた観客は物足りなさと同時に安堵を感じているのではあるまいか。
作品情報
脚本/監督 :ゾーイ・リスター=ジョーンズ
アメリカ映画、2020年製作
妄想パンフ
色々な角度から「魔女」を分析する内容で、読み終わると映画の内容と共に、魔女になるための知識が一通り身についているような作り。