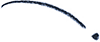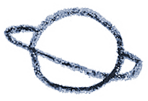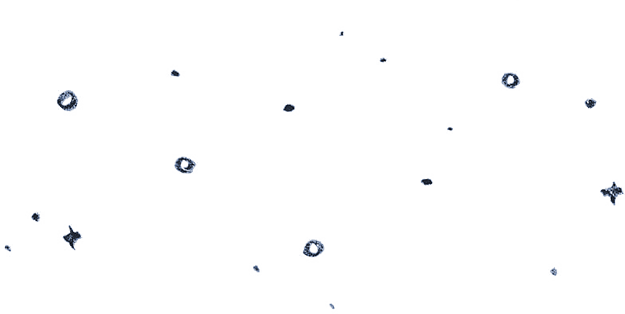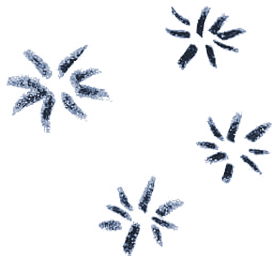文=小島ともみ
アルマ(マレン・エッゲルト)はベルリンの博物館で楔形文字の研究に打ち込む学者。世間を驚かせる世紀の大発見を間もなく発表できるとあって、仕事への傾倒ぶりにも拍車がかかっている。しかし決して独りよがりのタイプではなく、部下たちとのコミュニケーションは上々、上司とも良い関係を築いており、職場の環境は申し分ない。そんなアルマの悩みの種は研究資金。上司からの提案を受け、報酬を目当てにある企業が極秘で行う実験に参加することを決意する。それは、全ドイツ人女性の恋愛データを学習し、外見や性格もアルマ好みにカスタマイズされ、「完璧な伴侶」として振る舞うことができる超高性能AIロボットのトム(ダン・スティーヴンス)と三週間、生活を共にして「使用感」をレポートすることだった。初めて顔を合わせた瞬間からロマンティックモード全開で甘い言葉を囁き、アルマをドン引きさせるトム。一人と一体は三週間のミッションをクリアできるのだろうか?
スパイク・ジョーンズ監督の『her/世界でひとつの彼女』(2014)で主人公セオドアが恋するのは、声だけの存在のAI。ドゥニ・ヴィルヌーヴ監督『ブレードランナー2049』(2017)でKと一緒に暮らすジョイも同じく実体をもたず、Kとの関係も対等というより従属的だ。本作のトムは違う。性的にも機能する「肉体」を備えている。見た目も性格も100%自分好み。何をやらせても完璧で、その上ひたすら自分のことだけを考え、愛してくれる。そんな存在を孤独な人間に与えたら、過剰な自己肯定モンスターが誕生してしまいそうだが、主人公のアルマは出来すぎた女性で、文句のつけようがない好条件をまえにしても決して自分を甘やかさない。それどころか、人間の底知れぬ欲望を知り恐怖する彼女は「ちょっとした衝突」というアルゴリズムを忍び込ませてほしいと提案する。
アルマは自分を律することに長けている女性だ。逆にそれが欠点でもある。周囲からは「良い人」とみなされ、それが呪縛となってますます自分を内へ内へと押し込めてしまう。自律はまた、アルマにとって自分を守る最後の砦でもある。中年とよばれる年代にさしかかり、周囲が次々と伴侶をみつけ、子を、家族をなすなかで、ひとたび孤独を自覚してしまったらつらすぎて生きていけなくなるのではという危惧感を抱えているようにみえる。だから、心に入り込んでこようとするトムに対して必死に抵抗する。瞬時にさまざまなデータを取得し、先回りして軌道修正してくる相手に太刀打ちしようだなんて負け戦もいいところだけれども、ここで受け入れてしまったら、今度は「理想の相手を失う恐怖」と闘わなければならない。トムはほぼ永遠の命を保証されているロボットだが、実験体であり、期間が終われば回収されてしまうのだ。
(とはいえ、じつは街角で偶然出くわした他の被験者によって「三週間を永遠にできる方法」が示される。これによって、アルマは「喪失の孤独」からは逃れることが可能になる一方で、ジレンマをおぼえることになる。アルマをみずからの抱える問題に直面させる分水嶺として非常に効果的なエピソードだと思う。)
「喪失の恐怖」をめぐっては、二つのエピソードが出てくる。ひとつは、アルマ自身の肉体に起こったこと、もうひとつは、アルマの家族にかんすることだ。いずれもアルマの意思とはかかわりなく突然に起こり、なすすべもなく、手をすり抜けていってしまう。ひとは、濃淡の差はあれども、幾つもの出会いと別れ(あるいは失敗)を体験して人生の仕組みを受けいれる。わかってはいても、いざその時が訪れると心はなにがしかの傷を受け、時間が癒してくれることを願って待つしかない。心はゴムのようなものではないかと思う。放置すれば加水分解してべたつき、ぼろぼろになるし、あまり伸び縮みさせるとくたびれてしまう。激しく引っ張れば一瞬で切れる。アルマの心はいくたびかの伸縮を経て劣化し、弾力性を失いかけている。トムとの最初の出会いの場面で、アルマは試問する。リルケのあの詩の何行目は、とか、桁数の多い数字の計算だとか。そうして機械としての完成度の高さを確認すると、今度は人間性を問う質問をする。「想像しうる最も悲しいことは?」。トムの答えは、おそらくはこの種の製品としての特性、あるいは実験の趣旨に鑑みてプログラムされたものだと思われるが、弱りかけていたアルマの心を捉えたに違いない。「勝負」の行方はこの時点で決まっていたのだとも言えるかもしれない。
どこまでも甘いダン・スティーヴンスの完璧な恋人ぶりに酔いつつ迎える最後、アルマの選択はレジリエンスをみせ、希望を与えてくれる。この作品が投げかけるのは、孤独を認めること。それを惨めに思う必要はない。間違いなくあなたの一部なのだから。問題はそれを他人のせいにするのではなく、受け入れられるか。さもなくは、みずから開かれるしかないのだ。パンデミックにより、ひととの親密な交流が絶たれて久しい私たちは、実体を伴う存在として社会で生きるすべを忘れかけているかもしれない。ソーシャルメディア上でのデータのやり取りではない、身体と身体、心と心の交流。そんな日々が戻ってくるかはともかくとして、社会的動物としての自己のあり方をあらためて考えてみようと思わされる作品である。
作品情報
監督:マリア・シュラーダー
出演:ダン・スティーヴンス、マレン・エッゲルト、ザンドラ・ヒュラーほか
2021年/ドイツ映画/ドイツ語/107分
公式サイト
パンフ情報
【奥付情報】
A5変形/縦/カラー/24頁
発行:松竹株式会社事業推進部
デザイン:大寿美デザイン
印刷所:株式会社久栄社
定価:880円(税込)
関連パンフ情報
『her/世界でひとつの彼女』(2013)📚
表紙が素晴らしい。パンフには主演のホアキンインタビュー、キャストコメント、理想化されたロサンゼルスの街や音楽についてのコラムなどが掲載。監督スパイク・ジョーンズの最新作はビースティ・ボーイズのドキュメンタリー。#映画パンフは宇宙だ#PATUREVIEW pic.twitter.com/KSw1o1ozYN— パンフマン/Pamph-Man (@pamphman) February 13, 2022
『ブレードランナー2049』(2017)📚
Kの相棒ポリススピナーを大胆に配置し銀色で縁取った瀟洒な表紙。基礎知識に加え、カルト的人気を誇る前作の続編という難題に挑むに際し何を継承し、どう構築したかを紐解くインタビュー、解説を採録。ドラマ版2099も気になるところ#映画パンフは宇宙だ#PATUREVIEW pic.twitter.com/mGNOAlttrx— TOMOMEKEN (@Drafting_Dan) February 13, 2022