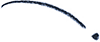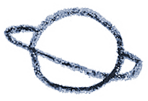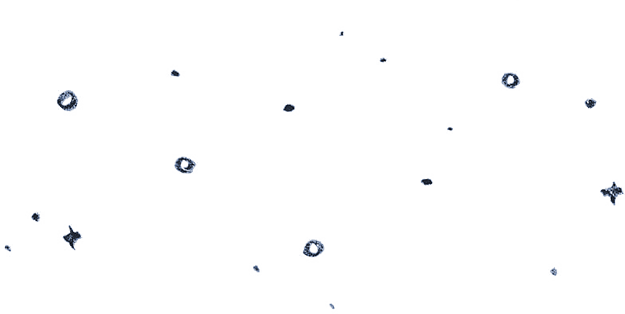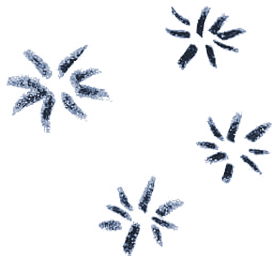文=小島ともみ イラスト=學
私は西部劇を好んで観るが、このジャンルの作品の多くは今のご時世に照らせばあるまじき設定の宝庫で、冷遇されてやむなしだとは思っている。ヒーローは決まって「白人」の「男性」だし、女性はといえばたいがい金で買われ、奉仕させられ、虐待される役回り。少数民族や有色人種は奴隷などの被虐待者か悪役だ。しかもそれらはすべてヒーローの強さと正しさをまつりたてるための添え物にすぎない。人種やジェンダー、宗教に対する差別の問題をわずかにでも含まない作品はないと言ってよい昨今の潮流にあっては、かつての西部劇はもはや絶滅必至種である。
そんな西部劇もここ数年は脱構築に励んできた。『荒野の七人』をリメイクしたアントワーン・フークア監督の『マグニフィセント・セブン』で主役を演じたのは、「黒人」のデンゼル・ワシントン。奴隷解放後のアメリカで黒人のカウボーイは決してまれな存在ではなかったのに、西部劇で主役をはることはほとんどなかったのを考えれば画期的な作品である。七人の中には原住民やアジア系も含まれ、女性も銃を取って闘う点もちゃんと今にのっとっている。マルティン・コールホーヴェン監督の『ブリムストーン』は従来型の西部劇の文脈をなぞりつつ、男性から一方的に暴力をふるわれ搾取されてきた女性の目線で「有害な男性性」の醜悪さと害悪をえぐり出してみせた。この流れのなかで登場した『パワー・オブ・ザ・ドッグ』を、私はかつての西部劇が礼賛してきたモノ、今の世で行き場をなくして彷徨うモノに引導を渡す憑物落としだと思った。
『パワー・オブ・ザ・ドッグ』は一九六七年にアメリカで発表された同名小説を映画化した作品である。原作者のトーマス・サヴェージは、自身が幼い頃に過ごした牧場での経験や当時のアメリカ西部の生活文化を取り入れたウエスタン小説の書き手としてよく知られる作家だ。本作中に登場するアルコール依存症に陥るローズや、愚直で温厚な牧場主の片割れジョージ、ジョージの兄で家父長的にふるまうもう一人の牧場主フィルは、それぞれ自身の家族を幾ばくかモデルにして創られたと聞くと、フィクションとはいえ一九二〇年代のアメリカ西部が透けてみえてくるようである。そして、力を行使し犠牲をいとわない開拓精神の夢とロマンの痕跡を抱えた時代のアメリカを、植民地主義に苦しめられ開拓される側であった過去をもつニュージーランド生まれのジェーン・カンピオンが手がけたのは興味深い。

一九二五年のアメリカ、モンタナ州。牧場経営で成功をおさめているフィルとジョージの兄弟は体格も性格もまるで正反対だ。長身ですらりとしたフィルはイェール大学を出た秀才でラテン語を嗜み楽器を弾く読書家のインテリだが、普段は口が悪くて皮肉屋、差別主義者的な一面も有している。しかし気取ったところはなく、むしろ「臭いのが好きだ」と言って風呂に入らないなど、粗野な態度で「男らしさ」を体現してみせ仲間を魅了し、絶対的な信頼を得ている。弟のジョージはずんぐりとした小柄な男で(フィルに「fatso(太っちょ)」とからかわれている)、落ちこぼれの口下手だが、温和で優しく堅実である。ビジネスパートナーとしても信頼し合い手堅く商売をしてきた二人の生活にある日、変化の兆しが訪れる。兄弟と雇われ人たちが出入りする食堂兼宿屋を女手ひとつで営むローズと、その一人息子で大学生のピーターとの出会いが兄弟のあいだに溝をつくり、フィルが「男らしさ」の裏側に押し込めていたものをあぶり出していく。

前夫の酒と暴力に苦しめられて離婚したローズが、いわゆる非モテ風だが実直でおよそ暴力とは縁のないジョージのプロポーズを受けたのは平安な生活の希求に加え、たしかにフィルが指摘したとおり、息子の学費を心配しなくて済むという経済的な理由もあったかもしれない。しかし当時の女性たちが、労働に参加できる風潮が出現してきたとはいえ、家庭を守る良き妻、子らの良き母親を理想像とするキリスト教的な精神構造を基盤にしていた社会で職に就くのはまだ困難だったことを考えれば、合理的な判断ではある。人たらしの兄と違い非モテを自覚していたジョージにしてみれば、もしローズが自分の財力に惹かれたのだとしても、家庭を築くまたとない機会だ。連れ子のピーターは大学生で学期が始まれば寮で生活をするわけだから、二人だけの生活を楽しむこともできる。互いに社会のなかでは高くない層に位置づけられた者同士が望める最大の幸せの構図に、果敢に西へ拡大を続けた開拓精神の爪痕はこうした人々が埋めていったのだろうと想像してしまう。
問題はフィルである。共同経営とはいえ牧場仕事のすべてで一枚も二枚も上手なフィルにジョージは頼りきりなのだが、フィルもジョージと寝室をともにするなど精神的に依存している部分がある。そのジョージをいわば「取られた」フィルは、持ち前の知性と底意地の悪さを発揮してローズを精神的に追い詰め、さらには女々しいとあげつらっていたピーターを手懐けてローズを孤立させようとする。フィルの世界に女は不要なのである。では、なぜそこまで女性を憎むのか。ここから物語は一気に現代的なテーマへとつながっていく。
フェミニズムの台頭によって女性の権利・地位向上を求める声が高まり、家父長制の害悪が指摘される一方で、近頃は「有害な男性性」に苦しめられているのはなにも女性ばかりではなく、男性もその「有害な男性性」が構築する社会の犠牲者として認識されるようになってきた。例えば従来は「男らしくなく恥ずべき」と秘匿されてきた人前で泣く、つらさや苦しさを訴えるといった行為は、個々人の心の健康を保ち、ひいては社会の健全化につながるとして推奨されはじめている。最近、男性が他人とつらい体験を分かち合い積極的に泣くことのできる場を提供しているイギリス人男性の活動を知り、少なくとも私の前では一度も涙をみせたことのない昭和十七年生まれの父がどんなふうに感じるのか聞いてみたくなった。
タイトルとなった「パワー・オブ・ザ・ドッグ」は旧約聖書の「詩篇」二二篇二〇節からとられたものだ。「わたしの魂をつるぎから、わたしのいのちを犬の力(the power of the dog)から助け出してください」、十字架にかけられて苦しむイエスが神に投げかけた嘆きである。ここでいう「犬」とはイエスの処刑を決断したピラトだと考えられている。劇中では、フィルが愛した景色のなかに「犬」の影が現れる。気づいたのは自分だけと自負するフィルをまえに、ピーターはあっさりとその影を見てとる。フィルも泣くことができたなら、ジョージ、ローズ、ピーターの三人と違った関係を築けただろうか。フィルに取り憑きフィルを抑えていた「犬の力」とは何だったのか。この点は原作同様、映画でも明白には描かれていない。だからこそ、フィルの抱えていた暗部がいつまでも胸のうちにこだましてやまない余韻を残す。『パワー・オブ・ザ・ドッグ』は弱さを吐露し、ありのままの自分で生きることを自己も他者も許さなかった時代の男たち、「犬の力」の束縛から逃れられなかった男たちへ、ジェーン・カンピオンが手向ける鎮魂歌である。
作品情報
『パワー・オブ・ザ・ドッグ』(原題:The Power of the Dog)
監督:ジェーン・カンピオン
キャスト:ベネディクト・カンバーバッチ、キルステン・ダンスト、ジェシー・プレモンス他
作品公式サイト(https://www.netflix.com/title/81127997)※2021年12月1日より配信予定
128分/カラー/英語/2021年/ニュージーランド・オーストラリア/Netflix
関連パンフ情報
『ブロークバック・マウンテン』(2006年)
発行日:2006年3月4日
発行・編集:株式会社ワイズポリシー
印刷:多田印刷株式会社
定価:700円(税込)
#PATUREVIEW
『ブロークバック・マウンテン』故ヒース・レジャーとジェイク・ジレンホールが紡ぐ永遠の愛。アメリカの強さ、逞しい男の体現の象徴とみなされるカウボーイ像に苦しめられた男たちの物語でもあります。見開きを使った写真の美しさに打たれ映画に戻っていきたくなるパンフレットです。 pic.twitter.com/T3EWXdtwrW— TOMOMEKEN (@Drafting_Dan) November 22, 2021
『ダラス・バイヤーズ・クラブ』(2014年2月22日)
発行:ファインフィルムズ
デザイン:伊藤正治(MK)
印刷:三永印刷
定価:500円(税込)
#PATUREVIEW
『ダラス・バイヤーズ・クラブ』AIDSは同性愛者の病気という偏見が強くあった80年代米国。ロデオを愛する異性愛者の男が病を得て自身の中の「有害な男性性」に気づき克服していく。HIV/AIDSと闘う人を支援する団体の方の取材に基づいた寄稿が伝える当時の米国世相に映画への理解が深まる。 pic.twitter.com/oPFWb3hIIp— TOMOMEKEN (@Drafting_Dan) November 22, 2021