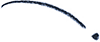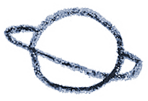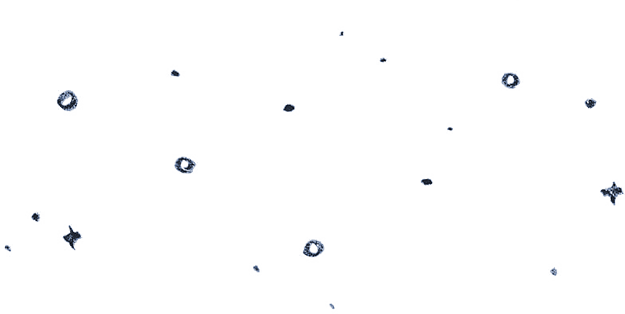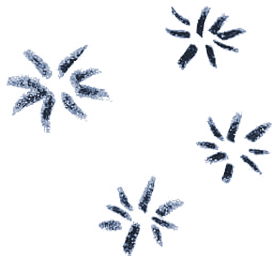文=小島ともみ
「『スワン・ソング』は急速に消滅しつつあるアメリカの『ゲイ文化』へのラブレターだ」とトッド・スティーヴンス監督はいう。故郷オハイオ州サンダスキーを舞台に、監督が十代のころ魅せられた実在の美容師パット・ピッツェンバーガー(1943-2012)をモデルにして描かれた作品。断片的でちぐはぐな印象を受ける場面もある。しかしそれがかえって記憶の底からかき集めた思い出を散りばめているかのようで、ノスタルジーをそそられる。なによりウド・キアの魅力のまえには、そんなことなど取るに足らない欠陥、にすらも思えない。
どんな端役でも強烈な印象を残す怪優が本作で扮したパットは、かつてはサンダンスキーきっての美容師として名を馳せたが、今は引退して介護施設で無為に日々を送っている孤独な老人だ。ある日、一番の顧客で町の名士だったリタが亡くなり、遺言書にしたがって彼女の弁護士がパットのもとを訪れる。死出の旅に向けパットに髪を整えてほしいというのだ。「酷い髪のままで埋葬しなさい」と言い放つパットとリタのあいだには一体何があったのか。逡巡の末、施設を抜け出してサンダスキーに向かったパットは、道具箱にしまい込んでベッドの下に押し隠してきた埃まみれの過去と幽霊に立ち向わざるを得なくなる。
AIDSへの偏見、同性の配偶者が認められなかったがゆえの悲劇。親友にも見捨てられた。フラッシュバックのように何度もあらわれるデヴィッドとの思い出、謎の友人ユニースやパットの一番弟子だったディー・ディーとの会話から、パットの歩んだつらい半生が浮き彫りとなる。目の前では二人の子どもを連れた男性カップルが歓声をあげながら楽しげに遊んでいる。「あれがゲイなら私たちは何?」と問うパットの声に、しかし怒りはない。
そんなのひどすぎる、理不尽だ、と今ならば多くの人が思うに違いない。あるいは、思うべきだ、と感じるだろう。例えばHIV感染者やAIDS患者への偏見が薄れるまでにはじつに40年近くかかった。その裏側にパットのように苦しみながら黙るしかできなかった人たちが大勢いるはずだ。啓蒙期に入った社会では、そういった人たちのことがおおやけに語られ、書き記され、映画にもなってきた。勇気ある人たちの物語として。とても美しく崇高で胸を揺さぶられるし、時に涙も誘われる。知ることができてよかったと思う一方で、生々しい出来事や苦い経験を思い出させられ、またなおも渦中の只中にいて、傷つく存在があることも忘れてはならないとも思う。

当事者が描いた当事者の物語を非当事者はどのように受けとめればよいのだろうか。煩悶する間に、監督は当事者に向けてあたたかなメッセージを発していた。失意のなかで無益に朽ち果てていくだけと投げやりだったパットに訪れた思いもかけない瞬間。それは誰にも等しく響くだろう。喪失を悼み寄りそうところから踏み出すと同時に、気持ちのよさだけで消化するなと洒脱ななりのウド・キアが語りかけてくる。ゲイ映画のその先へ。そこに本作の醍醐味がある。
妄想パンフ
「パットにしか着こなせない」とある人物が選んでくれたペパーミントグリーンのスーツにならって、ペパーミントグリーン一色の装幀に、モア、Vivante、カット鋏、指輪を散らす。裏表紙一面にパットとリタをつなぐシャンデリアを。中表紙には海外版ポスタービジュアルを使いたい。
作品情報
『スワン・ソング』(原題::Swan Song)
予告編はこちらから
監督:トッド・スティーヴンス
105分/カラー/英語/日本語字幕/2021年/アメリカ