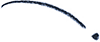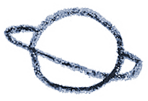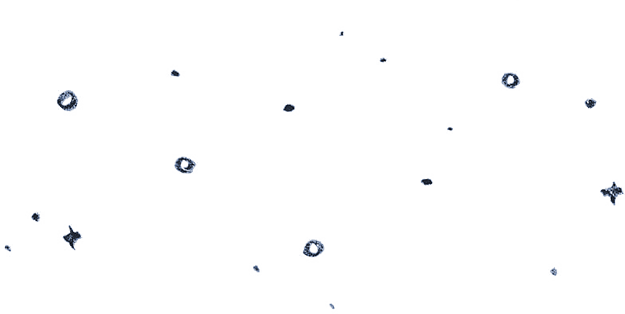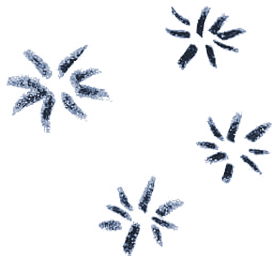文=竹美
同作の名前を初めて目にしたのは、確か、漫画『究極超人あ~る』だったと思う。登場人物が、「カルメン故郷に帰る」と呟いたら、「古いわね」と突っ込まれていた。また、『異人たちとの夏』(1988年)で、風間杜夫と名取裕子が家で観ていた映画も同作である。これを後で見たときはびっくりした。
1950年頃、浅間山山麓の村に、東京浅草でストリッパーをやっている女、リリィ・カルメン(本名おきん)(高峰秀子)が、その友達のマヤ朱美を伴って里帰りしたことで巻き起こる騒動を描いたコメディ作品。田舎と都会、逸脱と共同体秩序、芸術と大衆の欲望、娘と父親等のコントラストを、GHQ占領期独特の明るい総天然色の光で映し出す。
日本初の国産カラー映画に、このような素っ頓狂な物語が選ばれたことをまず喜びたい。本作は日本を代表するクィア的な映画の一つとして考えられている。2020年、早稲田大学坪内博士記念演劇博物館が企画した「Inside/Out――映像文化とLGBTQ+」という展示では、同作について「占領期における肉体言説と解放のシニフィアンとしての女性身体」の代表的な例として知られる」としつつ、主役の女性カルメンが「本作のクィアな受容を同時に招待する」と評した。GHQ占領期特有の空気がグラマラスで自由な女性というイメージを通じて出てきているということ、そして、カルメンの放つ自由奔放さによって、「この映画ってあの辺が実はこういう意味じゃないの?」とほくそ笑みながら楽しむファンの「読みの快楽」も得られると言っているのである。
本作は対比だらけである。カルメンがストリップを「芸術」だと思っているのに、村の偉い人(校長先生)は、映画冒頭で流れる(いささか辛気臭い)歌曲「そばの花咲く」を「芸術」と言ってありがたがる。また、カルメンたちのド派手なファッションとメイク(今で言えばドラァグクイーン的だ)と、村人たちの地味な服装の対比、「ストリップ」=「人前で裸で踊る」仕事をする娘のことが恥ずかしくてならないが深く愛してもいる父親と、その気持ちに無頓着なカルメンの対比。戦争で失明して戻ってきた音楽家から、借金のカタに大切なオルガンを取り上げてしまう金持ちの興行主と、それをなじる校長先生。音楽家の男に惚れていたことをあっけらかんと語るカルメンと、献身的な妻。
様々な在り様を対比しつつ、それでいて決定的に誰かを批判するようなこともない。皆が善意でいるのに起こる哀しさと苦しみが合わさって、実は何一つ解決されないまま(オルガンの問題だけは偶発的に解決?)、カルメンたちは笑顔で東京に帰って行ってしまう。社会というのは結局、変わらないと言っているようにも見える。
本作に関し、カルメンは子供の頃に頭を牛に蹴られてから頭がおかしくなってしまった、という形で、「病理」によって彼女の自由奔放が受容されているという解釈がある。確かに嘲笑しながら、「まァ、常識から外れているけど、あの人は特別だから、そういう人だからいいんだよ」という風に雑に受け入れる態度が見える。
ところで、そのような「恥ずかしい娘」を一族の恥として殺すという発想に結びつく社会もある。本作には名誉殺人のような発想は作中には無い。日本では、必死でそれをひた隠しにはしても、当人(特に女性)を殺すまではしない。では彼女の様子を「病理」として語ることで、社会はそれを「受容」していると見ていいのだろうか。それは「寛容さ」なのだろうか。
日本に定着するかどうかの段階にあるアイデンティティ・ポリティクスの考え方に基づけば、それはマイノリティや弱者に対する抑圧や差別の力であるからして、決して容認されるべきではないという結論になる。そう読むと、上記のような「まァいてもいいじゃないか」という態度は「マジョリティのおめぐみ」でしかないし、抑圧の構造は変わらないことが、繰り返し非難されている。
カルメンの自由さをそのまま受け入れているのは姉(望月優子)だけ。そして、カルメンにある種の「鈍感さ」があるが故に、彼女が周りの反応に傷ついているかどうかが描かれていないおかげで、本作は観ていてつらくならない。あの世界では、カルメンは、知らぬ間に、世間に対して「嗤われる自分」と自由奔放さをトレードしていると言えるのかもしれない。「わきまえない」という言葉がトレンド入りしたが、カルメンはどうだろう。あれも一つの「わきまえない」姿だろうか。
世の中はなかなか変わってくれない。「なぜ今、こうじゃないんだ」と怒る気持ちも湧いてくる。なぜ、同じ仕事をしても賃金が低いのだろうか。なぜ私の彼氏には労働ビザが許されないのだろうか。なぜ日本では我々は婚姻ができないのか、なぜ夫婦別姓がダメなのか、なぜ片方の性別の人はわきまえるべきだと言われるのか…日々大殺界のように怨嗟の声が聴こえる。
しかし同時に、日々を生きる人間としての我々は、「変わってくれない世の中」の中で、ときに常識を圧倒し、少しはみ出しながら一瞬を生きて見せることができる。カルメンと朱美のように、村の男達の目線なんかそっちのけで、奇妙な踊りを見せつけ、勝利の物語を一瞬自分のものにする。木下の映画は、今の我々には察知が難しいものの、GHQ占領期の明るい光を投げかけている。世の中の面倒臭いしがらみをきっちり守るように見せかけて、突如とんでもない逸脱を見せてくれるのである。それは確かに嘲笑され「嗤われる」ことだ。カルメンと朱美は、世の中の面倒臭いしがらみや嘲笑を踏み台にしながら、それを一顧だにしないむっつり顔で踊る。そのようなむっつり顔をこっそり盗み見た子供達の心に、ド派手な衣装とメイクがしっかりと根を張るかもしれない。そして、将来、「面倒くせえ世の中」の境界線を少し書き換えたかもしれない。映画の中の自由奔放さは、確実に後の時代の社会を変えてきた。
周りは寛容じゃないかもしれないが、自信を以て、「少しだけ」逸脱すればいいと思う。それは必ず誰かの力になるはずである。『カルメン故郷に帰る』は、そんな「逸脱」する皆さんをいつまでも、総天然色で応援してくれる映画である。
作品情報
『カルメン故郷に帰る』
監督:木下恵介
出演:高峰秀子、笠智衆、佐田啓二、佐野周二、望月優子他
製作年:1951年
関連パンフ情報
#PATU #patureview
何でもホラーにしちゃう私の趣味により『田舎に帰る娘が地元に持ち込んだ何か』という観点で、『ゲットアウト』は『カルメン故郷に帰る』の暗黒版である。『ホラーにコメディで学んだ全てを注ぎ込むのは楽しかった』と語るジョーダン・ピールの圧勝。ブラムハウスの目利きも怖い。 pic.twitter.com/HNW1mxcfup— 竹美 तकेमी తకెమి 다케미 (@tonchantonchan) July 4, 2021