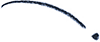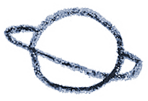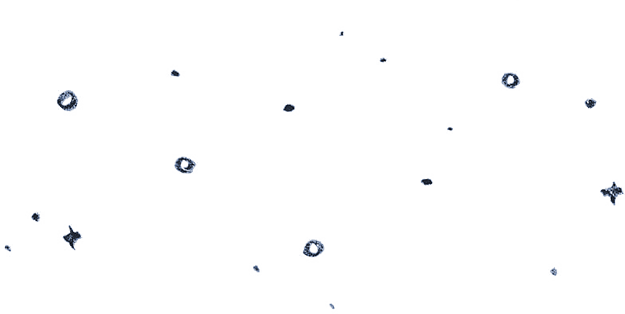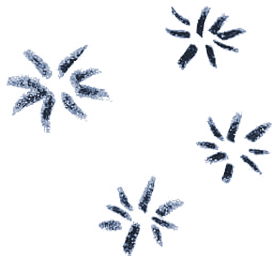文=ながせ
本作の主人公は戦争で夫を亡くした女性、フローレンス(エミリー・モーティマー)。彼女は、本と夫を愛して過ごしていた幸せな生活を戦争に奪われ、しばらく悲しみに沈んでいましたが、イギリス東部の海辺のある街に、かつて夫と夢見た書店を開こうと動き出します。映画ではそんな彼女が夢を叶えようと奮闘する中で起こる様々な葛藤と、自分の住む地域に長く存在しなかった書店ができることに戸惑う街の人との交流の様子が描かれます。
フローレンスが夢見た、小さいけれど、内容を吟味し、彼女が信じるに値する書物を選び抜いて並べる思いの詰まった書店。フローレンスはその店を構える場所を半年以上かけて選びます。しかし、彼女が夢の実現のための場所に選んだ“オールドハウス”は、街の有力者であるガマート夫妻が目をつけていた物件でした。自分たちの思惑に沿わない行動をとるフローレンスを快く思わないガマート夫人は、住民や自分の親戚を巻き込んで、フローレンスとオールドハウス書店を排除しようとします。
一方、街の有力者のひとりで、偏屈な頑固者として街の皆が恐れている紳士ブランディッシュ(ビル・ナイ)は、読書が好き。彼はオールドハウス書店が開店すると、書店が選書した本を購入したいとフローレンスに宛てて手紙を書きます。その手紙には彼女が街に書店を開くことを歓迎するという内容とともに、「かつて街で起きたとある事件以降、書店を開こうという勇気のあるものは、これまで1人もいなかった」と書かれているのでした。
個人的には、書店を開くことが「勇気あること」として認識される社会には違和感を覚えますが、その社会を作っている人々、つまりこの映画で描かれる街の人の多くはそれぞれが単純な「良いひと」でも「悪いひと」でもありません。保守的な街で、それぞれが自分の生活を守るため、必死に暮らしている。
そんな街において既に経済力と権力を手にしているガマート夫妻は、毎日を必死に生きる住民たちに、自ら考えることや余裕を持って暮らすことを望んでいるようには見えません。ずっと自分たちの意のままに動いてくれれば良いのだと。そして、法律までをも自分たちの都合の良いように変えてしまうのです。
関わる人たちそれぞれに心を開きかけて、どこか疑いながらも信じてみようとしては、その度にがっかりするフローレンスに、店を手伝う聡明な少女クリスティーン(オナー・ニフシー)は「あなたは優しい。優しすぎるわ」と言います。
フローレンスは、度重なる嫌がらせにも負けず、微かな人々の良心や、自身の信じるものに支えられながら、なんとか書店の運営を続けるのですが、最終的には店を手放す決断をします。
これでもか!という嫌がらせの連続に、フローレンスは勇気を持って立ち向かい、しかし自分のために、ある時点で闘うことから一歩引く決意をする。信念を曲げず、闘い続けることは、勇気ある行動ですが、そう簡単ではありません。けれど彼女は相手を負かそうとしたり、攻撃することはしません。
それは彼女の目的が、戦争という争いに巻き込まれて命を奪われた夫との夢を叶えるという想いに基づいたものであり、結局は命つきればどんなに素敵な夢もどんなに気高い想いも意味をなさないという思いがあったからだと思います。争いを仕掛けられたフローレンスは、その対立から自ら降り、こだわり抜いて築いた店を捨てます。それは確かに挫折かもしれませんが、彼女が夫と夢見た未来に可能性を残す選択をした、と解釈することもできます。
高橋諭治氏によるこの映画のパンフレットの解説文では、本作を監督したイザベル・コイシェ監督のことを「感傷に流されず、目には見えない人生や人間の機微を写し取る」と評しています。さらに、彼女の作品は「メランコリックではあっても、センチメンタルに流されることがない。最もドラマのエモーションが高まる感動的なシーンさえも編集でズバッと絶ち切り、お涙ちょうだいのメロドラマには仕立てない」とも書かれています。
コイシェ監督がこれまで作り上げた映画、例えば『死ぬまでにしたい10のこと』(03)や『あなたになら言える秘密のこと』(05)などがそうであったように、本作も辛い出来事を過剰にドラマチックにはせず、主人公が潔く生きていく姿が印象に残る作品です。
映画は、原作であるペネロピ・フィッツジェラルドの小説「ブックショップ」とは異なるラストに辿り着きます。コイシェ監督は原作者の家族に了承を得て、感傷に流されないながらも未来を感じさせるエンディングを描きました。それはあまりにも小さな一歩かもしれないけれど、この架空の閉塞的な街と、街の人々に、フローレンスの勇気がほんの少しの風穴を開けたのだ、と信じたくなるエンディングです。
また、この映画は主人公であるフローレンスの視点によって描かれるのではなく、第三者の視点から捉えられ、ナレーションによって物語が展開されます。
ナレーションを担当しているのは、レイ・ブラッドベリの小説「華氏451度」をフランソワ・トリュフォー監督が映画化した際に主演を務めた俳優、ジュリー・クリスティです。
なお、「華氏451度」はこの映画では物語を動かす、鍵となる作品として登場するのですが、原作には登場しません。
自身も読書が大好きで、映画制作者としてフローレンスに自分の姿を重ねたと語るイザベル・コイシェ監督は、映画のために、本の所持や読書が禁じられた架空の社会を舞台とするこの小説を、物語の鍵を握る作品として選びました。
映画にはいくつかの小説が登場しますが、ウラジミール・ナボコフの「ロリータ」以外はすべてコイシェ監督が自ら選書したそうです。
ちなみに、映画のエンディングで少女クリスティーンが手にしているのはリチャード・ヒューズの「ジャマイカの烈風」。
私は、映画のエンディングにイザベル・コイシェ監督が込めた映画と本や読書を愛する者としての強い想いと痛烈なメッセージに圧倒されて、映画館を後にしました。
余談ですが、私がこの作品を鑑賞した恵比寿ガーデンシネマは、今年2021年2月末をもって一時閉館となりました。(恵比寿三越の閉店と恵比寿ガーデンプレイスの改装に伴う閉館。これを書いている2021年3月現在も閉館中で、再開時期は未定とされています。)
恵比寿ガーデンシネマのパンフレット売り場には、いつも作品の関連書籍が一緒に並べられており、個人的に特に好きなパンフ売り場のひとつでした。この作品の鑑賞後も思わずパンフレットと原作と「ロリータ」の単行本を購入しました。
昨今、パンフレットが作られない作品も目立つようになってきましたが、映画を鑑賞したあとのワクワクや興奮した気持ちのままパンフレットを持ち帰り、帰り道や家でもその余韻を楽しむことが大好きな私としては、そんなパンフレット文化も、多様な作品を上映する映画館も、店主の想いの詰まった街の書店も、大好きなものはなくなってほしくないなぁ、と思う日々です。私の小さな行動も、誰かと、誰かの未来に繋がっている、と信じて。
作品情報
『マイ・ブックショップ』
原題:The Bookshop
監督:イザベル・コイシェ
出演:エミリー・モーティマー | ビル・ナイ | ハンター・トレメイン | オナー・ニフシー | パトリシア・クラークソン
イギリス・スペイン・ドイツ合作
製作:2017年
112分
パンフ情報
深いグリーンが印象的な表紙。背景の本棚が目を引く。
20ページ・A4定型
【奥付情報】
発行日:2019年3月9日
発行:ココロヲ・動かす・映画社◯
編集:ミモザフィルムズ
デザイン:大寿美デザイン