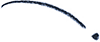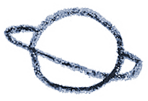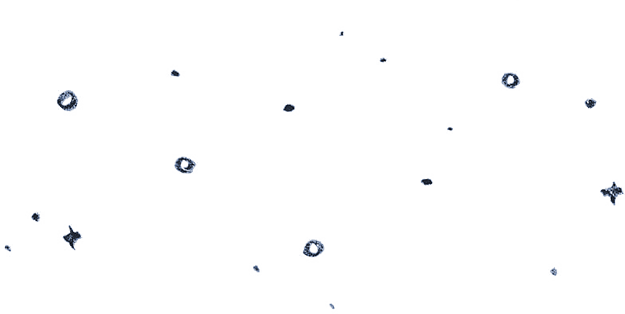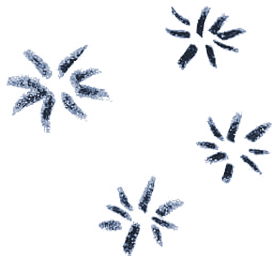文=小島ともみ ※映画の結末にふれている部分があります
外出を制限され、人との交わりを極限までたたれて、家のなかに閉じこもらなければならない――多くの人がそのストレスと恐怖を現在進行形で味わっているいま、この『ビバリウム』という作品は骨身にこたえるのではないかと思う。そこにパンデミックは存在しないが、生をたのしむ自由もない。極限まで追い詰められた愛し合う者同士が互いを精神的に、物理的に傷つける対立の構造は、それ自体でじゅうぶん胸をひりつかせるものがある。そこへもって監督のロルカン・フィネガンは、そのかろうじて残されたつながりさえも徹底して破壊しにかかってくる。
小学校の教師ジェマ(イモージェン・プーツ)と造園業者のトム(ジェシー・アイゼンバーグ)は若いカップル。二人とも現在の仕事を気に入っており、結婚はもちろん子どもを持つことにもまだ関心がない。ただし、近ごろ価格が高騰しつつある住宅事情を心配し、早めに安くて良い家を手に入れたいと考えている。二人はたまたま通りがかった不動産屋に興味本位で入る。どこか奇妙な店員のマーティンになかば強引に誘われて、二人は気乗りがしないまま郊外の新興住宅地「ヨンダー」へとおもむく。そこはまったく同じ規格の庭付き一軒家が果てしなく並ぶ巨大な住宅地だった。二人を「9番」という札のかかった家に案内したマーティンは、突然なにも言わずに車で立ち去る。残された二人も自分たちの車で帰ろうとするが、行けども行けども同じ家、同じ角、同じ道の堂々めぐりで気がつけば「9番」の家の前に戻ってきてしまう。疲れはてた二人は一夜をその家で明かすが、翌朝から真空パックに包まれた食品など生活必需品の入った段ボールが家の前に届けられる。そして、ある朝、置かれた箱の中には生きた赤ん坊が入っていた。ふたにはこう書かれている――「育てれば解放される」。
■短編『FOXES』とアイルランドの住宅事情
『ビバリウム』には元ネタになった作品がある。フィネガン監督が2011年に撮った短編『FOXES』だ(現在、VIMEOなどで無料公開中)。同じ表構えの家がずらりと並ぶ新興住宅地にぽつんと暮らす夫婦が常ならぬ世界へと横すべりしていく。監督曰わく、両作品に出てくる「街」はアイルランドに点在するバブルのなれの果て地「ゴーストエステート」なのだという。土地の価格が暴落して業者は撤退、なかには開発途中の状態で放置された場所もあった。少数の不運な購入者は売ることもできず、郊外の不便な地に建つ価値のない家のローンを未来にわたって返し続けなければならなくなった。がれきのそばで遊ぶ子どもたちには虐待の危機もある。終の棲家、イコール、ある意味で人生の終着点がそんな場所だと思うとたまらなくゾッとする。
■カッコウの托卵のエピソード
映画の冒頭には物語の展開を暗示させる映像があらわれる。有名なカッコウの托卵の様子だ。カッコウ科の鳥は卵を抱いている他種の鳥の巣に卵を産みつけ、親の役割をその巣の持ち主に押しつける。のみならず、巣の持ち主の卵よりも短期間でふ化したヒナは、持ち主の卵やヒナを巣の外に押しだしてしまう。哀れな親鳥は自分よりも大きな体をもつヒナになんの疑いも抱かずせっせと世話をし続けるのである。この「托卵」はしばしばホラーやSF映画のモチーフとなる。まさにそのものを描いているのが『死霊懐胎(The Godsend, 1980)』だ。悪魔の子を宿した妊婦が公園で優しそうな家族に取り入り、一家の家で女児を出産して亡くなる。誕生した女児は、義理のきょうだいたち四人を事故に見せかけて葬り、養父母の睦み事を邪魔し、母親を流産させ、父親にはおたふく風邪をうつして子種を殺す。父親は不可解な出来事を引き起こしているのはこの女児だと考えて追い出そうとするが、母親は女児を守ることを選び、家族は崩壊する。『ビバリウム』の二人は自分たちの子どもをもたない。だから、配達された赤ん坊は誰かを蹴落とす必要はないのだが、若い二人に誇張された育児の恐ろしさを植えつけ将来の可能性を摘み取り、「父親」と「母親」のラベルを貼りつけてコントロールする。二人はベッドをともにしてももはや性的な関係には発展しないのである。超人的な力をもった子どもが恐怖で大人を支配する展開は『光る眼(Village of the Damned, 1995)』、もしくは、フィネガン監督が目指した世界観のTVシリーズ『トワイライトゾーン』、その一話「こどもの世界(It’s a Good Life)」のようだ。無邪気で力のない存在の外観をまとい相手の攻撃力を奪いさる智略には歯がみしたくなる。届いた男児は驚異のスピードで育ち、耳をつんざく金切り声をあげ、二人の声マネをし、アメーバのような模様を垂れ流すテレビに見入って何かを学習する(『ポルターガイスト(Poltergeist, 1982)』でキャロル・アンが「テレビピープル」と会話する場面を彷彿とさせる)。薄気味の悪さから「それ」と呼び忌み嫌うトムにたいしてジェマは愛情をもって接しようとし、二人はいがみ合い、暴力さえふるうようになっていく。
■否定される「男らしさ」
悪夢版ウェス・アンダーソンといった優しくグロテスクなビジュアルで斬新な世界をみせてくれる『ビバリウム』だが、キャラクターの造型はホラー映画の伝統にのっとっている。ホラー映画のたぐいで不可思議を最初に察知し理屈を抜きにして受け入れるのはたいてい女性である。男性(もしくは男性的思考をとる者)は社会的地位や立場、科学への絶対的信仰にとらわれて信じることができずなんとか合理的な説明を見出そうともがく。ホラー映画の世界で「男らしさ」は愚かで嗤うべきものなのである。輪廻転生を描いた『オードリー・ローズ(Audrey Rose, 1977)』では、娘が死んだ他人の子どもの生まれ変わりだということを受け入れられない父親の頑迷さが娘を死に至らしめる。その点、『ポルターガイスト2(Poltergeist II: The Other Side, 1986)』の父親は、あの世の祖母とスピリチュアルにつながる母と娘たちを拒否せず、みずから心をひらいてその世界に入っていき、彼女たちと一緒になって悪霊に立ち向かう。異常な事態が生じたときに女性が男性よりも柔軟性をもって描かれるのは、その身体的特徴と切り離すことはできない。好むと好まざるとにかかわらず、女性には「入り口」があり、自分以外の他を受け入れて新しいものをつくりだす力があると考えられるのだろう。逆に男性器は自分以外の他に力や影響を及ぼす象徴であり、その持ち主には状況を力でこじ開けていく役割がふられる。『ポルターガイスト2』の父親は男だが、霊媒師に魔法の煙をふきこんでもらい「受容」によって力を得る。『ビバリウム』のトムはかたくなに男性性にしがみついて自滅していくのだ。そして、トムに代わって男性性を発揮し、力をもって制圧を試みるジェマもまた、同じ運命をたどる。
■日常にひそむジェンダー化の呪い
「ビバリウム」とは、観察や研究のため、自然の生息状態をまねてつくった動植物の飼育場である。「ヨンダー」には清潔な住居があり、子どもがいて、ケーブルテレビも完備、生活に必要な品はすべて無償で提供される。およそ人間という生物が暮らすには申し分のない環境がととのえられているようにみえる。もちろんこれらは人間を外形の特徴だけでしか分類することのできない「エイリアン」があつらえたものにすぎない。画一化された建物、街並み、パッケージ食品と同じく、ここで必要とされるのは「母親という女性」と「父親という男性」のみである。しかし互いに職を持ち自立した生活をおくっていた二人が、所与の条件によって無意識のうちにジェンダー化されていくさまはおそろしい。とりわけジェマは何度も「私はあなたの母親ではない」と繰り返して母親の役割を明確に拒否するのだが、結局は少年の疑似母となってしまう。『ステップフォードの妻たち(The Stepford Wives, 1975)』は女を良妻賢母として家庭に縛りつけたい男たちがつくりあげた「夢の街」だった(2004年のリメイク版は違う解釈をとるが)。誰かの視点でみた「完璧な環境」ほど不健全でゆがんでいるものはない。ぶつかり合うのはしんどいことだが、軋轢と矛盾こそが社会を偏向から救っているのではないかと思う。「ヨンダー」が求めるかつての理想的・伝統的家族のあり方に、私たちの多くはもはや戻れない。旧約聖書の創世記第一章にある「産めよ、増えよ、地に満ちて地を従わせよ」という神様の命令を超えて、目下のところネオリベ社会を生きているのだから。未曾有の孤立に見舞われた世界で観る本作は、不条理の恐怖というよりむしろ今ここにある危機を感じさせる。
作品情報
『ビバリウム』
原題:VIVARIUM
監督:ロルカン・フィネガン
出演:イモージェン・プーツ、ジェシー・アイゼンバーグ、ジョナサン・アリスほか
アイルランド・デンマーク・ベルギー合作
製作:2019年
97分
https://twitter.com/Drafting_Dan/status/1370255420221091847?s=20
関連パンフ情報
『オーメン』
関連パンフ(1)
『オーメン』(1976)
タイム誌評全訳など非ネット時代、昭和パンフの王道構成。
A4タテ定型/24ページ
【奥付情報】
発行日:昭和51年9月18日
発行所:東宝株式会社事業部
発行権者:廿世紀フォックス株式会社
印刷所:成旺印刷株式会社
定価:250円 pic.twitter.com/6rercFIHDU— TOMOMEKEN (@Drafting_Dan) March 12, 2021
『アダム-神の使い 悪魔の子-』
関連パンフ(2)
『アダム-神の使い 悪魔の子-』(2006)
デ・ニーロ好きにもあまり知られない模様の作品のパンフ…心意気が嬉しい!
A4タテ定型16ページ
【奥付情報】
発行日:2006年10月7日
発行:株式会社ザナドゥー
編集:岸川真
デザイン:宇田川薫(ウダガワデザイン室)
印刷:多田印刷
定価:700円(税込) pic.twitter.com/7gMW7p8tEx— TOMOMEKEN (@Drafting_Dan) March 12, 2021
『グランド・ブダペスト・ホテル』
関連パンフ(3)
『グランド・ブダペスト・ホテル』(2014)
B5タテ定型56ページ
【奥付情報】
発行日:2014年6月6日
発行権者:20世紀フォックス映画
発行・編集:(株)角川メディアハウス映像メディア部
編集:下田桃子
デザイン:塚原敬史、岩間良平(trimdesign)
印刷:大洋印刷株式会社
定価:820円(税込) pic.twitter.com/IJ1YEEeEq3— TOMOMEKEN (@Drafting_Dan) March 12, 2021