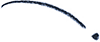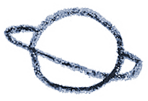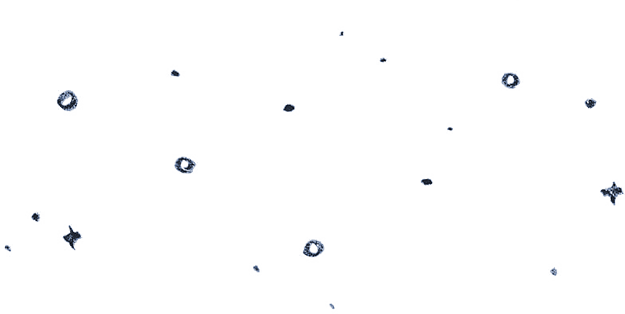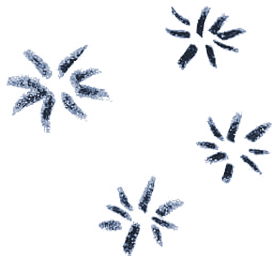文=小島ともみ
エンドロールが終わり場内が明るくなると、一緒に観ていた友人は「純愛だねえ…」とため息をついた。私にはまったく理解も共感もできなかったが、「渋谷系」という言葉が一世を風靡していた1999年、カッコいいとはきっとこういうことを言うのだろうと思った。PARCO「パルコスペース・PART3」がシネクイントに生まれ変わったこけら落としの作品『バッファロー’66』。イエスやキング・クリムゾンなどプログレを中心とした音楽はとても良かったし、真っ白な息をはきながら始終何かに耐えあらがうふうのヴィンセント・ギャロは実際に格好良かった。その後は急進派の共和党支持者としてならし、最近もInstagramでトランプ元大統領を熱烈に褒め称える投稿をしたり、そもそもこの映画の撮影中に共演のクリスティーナ・リッチの体型についてあれこれと言って彼女をひどく傷つけたらしい。そんなヴィンセント・ギャロの人となりはさておき、約20年ぶりにスクリーンに戻ってきた『バッファロー66』には「こんな作品だったのか」という驚きがあった。以下、妄想の限りを筆舌に尽くしてみようと思う。
ヴィンセント・ギャロの自伝的作品ともいわれる本作(ビリーの実家はギャロが育った家によく似ているとのことだ)でギャロが演じる主人公は、ビリー・ブラウンという名の30代の男だ。物語は、ビリーが投獄されていた刑務所を出所するところから始まる。街へ戻ったビリーは、バッファローにある実家へ向かう。両親には刑務所にいたことを告げていない。「政府の仕事で遠くにいた」と嘘をつき、さらには「妻を連れて行く」と大見得を切ってしまう。ビリーはたまたま飛び込んだダンス教室でレイラ(クリスティーナ・リッチ)を見そめて誘拐する。親の前で妻のふりをさせるためだ。ぎこちない両親との再会をレイラの明るさで乗り切ったビリーは、レイラを昔なじみのボーリング場へ連れて行く。ビリーにはこの街で果たさなければならないもうひとつの目的があった。彼が刑務所に行くはめになった男への復讐だ。待ち伏せのための時間つぶしに立ち寄ったモーテルで、ビリーはようやくレイラに心を開きはじめる。何かを察したレイラはビリーを引き留めるが、標的の男が経営するストリップ劇場にあらわれる深夜、ビリーは銃を手にモーテルを抜け出す。男の姿をみとめ、立ちはだかるビリー。男をにらみつけ、引き金に指をかける。ビリーは復讐をなし遂げるのだろうか?
このビリーという男、とことん鼻持ちならない。腹いせに他人を怒鳴りちらかし、差別用語を平気で口にする。悪態をついた舌の根の乾かぬうちに人の善意にすがる。応えてくれた相手をくみやすしと見るや、上から目線で理不尽な扱いをする。そもそも出所した足で誘拐という重罪に手を染めるなんて、常軌を逸している。そうしてかどわかしたレイラには対等な会話を許さず、両親の前ではひたすらに自分を立てるよう要求する。本当に嫌な男だ。ところが、物語の様相はビリーの実家訪問から少し変わってくる。孝行息子にはみえないビリーが、何をおいても出所後まず会いたかった両親という人たちに驚かされることになるのである。ビリーもたいがいだが、奇矯さでは両親も引けをとらない。地元アメフトチームの熱狂的なファンである母親は、お気に入りの試合を延々と大音量で流し続けている。そんな母親とは家庭内別居状態の父親は、何かの拍子でスイッチが入ると突然怒り出す。異様な家庭内の空気に居心地の悪い思いをしているうちに、母親がレイラにしめす幼いビリーの写真をきっかけに明かされる家族の過去にハッとさせられる。ビリーはネグレクトされた子どもだったのだ。
母親は、ビリーに関心がない。さも優しげにチョコレートを勧めるが、ビリーには子どものころからチョコレートアレルギーがある。「食べて顔を腫らしてただろう」と訴えても、母親は信じようとしない。出産と重なって伝説の試合を見逃したことを今でも根に持ち、「おまえを生まなければ試合が見られたのに」と恨みごとを言う。何十年と口癖のように言い続けてきたのだろうと容易に想像がつく自然さで。父親は、ちからでビリーの楽しみを奪うだけの存在であって、もちろんビリーには無関心。レイラが作り話でビリーがどれだけ素晴らしい人間かを披露しても聞き流し、むしろレイラが気になる様子だ。二人ともいないほうがましな親の典型のようである。
ビリーが誰にたいしてもけんか腰で、視線すらあわせることを拒否する態度をとり続けるのは、存在を否定され続けた自分を守る防御的拒絶であり、それでも「愛されたい」という願望のあらわれだ。彼の心は、幼少期に受け続けた傷で凍りついている。そうだとしてもレイラへの態度はあまりにもひどい。そもそもレイラとは一体、何者なのだろうか。なぐる、けるなどの身体的暴力は受けないが、自由と意志を奪われ、ビリーの気まぐれに引きずり回される。明かされるのは名前だけで、キャラクターとしての掘り下げは一切なされない。ミソジニスティックなロマン主義の犠牲者であり、自己愛性パーソナリティ障害を抱える男の感情のサンドバッグでしかないようにみえる。
美しい女性と愛に飢えた獣のような男、で思い出すのが「美女と野獣」の物語だ。よく知られているのはディズニー映画版だろうが、もとは1740年にフランスの作家ヴィルヌーヴ夫人によって書かれた異類婚姻譚だった。バリエーションは細部にあれども、物語の要点は、魔法使いの呪いによって獣の姿にかえられた王子が、恐ろしい外見にとらわれることなく内側にある穏やかで優しい心根を見抜いた女性に愛されることで救われるというものだ。『バッファロー’66』は物語構造のひとつにこの寓話を含んでいるように思われる。ビリーはレイラを価値のない愚かな存在とみなし、「言うことを聞かなければ殺す」と脅して自分の意に従わせる。レイラだけが、その暴力的なふるまいの奥底には愛されたいだけの臆病な少年がいることを見ぬき、愛情を寄せていく。酷い両親と対面したあとでは、ビリーの歪んだ性格と行為は虐待の連鎖によるものだと気がついたかもしれない。最新のディズニー映画実写版『美女と野獣(2017)』で、ベルは自分の意志を強く持った女性として描かれているのに比べたら、やはり『バッファロー’66』は、女性だけが一方的に「外見にとらわれず真実を見ぬいて無償の愛を注ぐ」という役割を振られる点で前時代的な男のファンタジーで成り立っていることは否めないだろう。しかし、それらはすべて虐待被害者が過去とトラウマを克服しようとする葛藤の表現だとしたら、ただの自己陶酔と切ってすてるわけにもいかない。モーテルでの入浴のシーンはとくに象徴的だ。膝を抱えてバスタブにつかるビリーは、最初レイラが浴室に入ってくることを拒む。レイラはたくみに距離を縮め、ついには温かいバスタブのなかで二人は向かいあう。ビリーは依然としてかたくなな部分を残してはいるが、風呂からあがるとレイラに体をあずけて幼児のようにつかの間の眠りにつく。ビリーはここで、追い求めていた理想の母親としてのレイラの手をかりて、この世に新しく生を授かったのではないかと思う。
『バッファロー’66』にかんしては、もうひとつ引きたくなる寓話がある。彼の唯一の友人だと思われるグーンとの関係はドン・キホーテの物語を想起させないだろうか。ビリーは自分の不運を、大金をかけていた試合で八百長をやらかした選手スコットのせいだと思い込んでいる(実際のところはとんだ濡れ衣である)。大スターだったスコットはすでに引退してストリップ小屋を営んでおり、そこそこの成功をおさめているようだ。ビリーはこの男を殺さなければ自分の心の平安を取りもどせないと考えている。巨人を退治しなければならないと風車に躍りかかるドン・キホーテそのものだ。少し愚かなグーンは、サンチョである。ビリーがどれほど酷い言葉を投げつけても、彼をうやまい、励まし、やさしく説きふせる。ドン・キホーテの物語では、風車に吹き飛ばされたドン・キホーテはサンチョから現実的な指摘を受けても目が覚めず、妄想の旅を続ける。『バッファロー’66』でビリーを現実に引きもどすのは、グーンの箴言というより、脳裏に浮かんだ、自分の死にも動じない薄情な両親の姿だ。ビリーがわずかにもっていた両親への愛慕の念を完全に手放した瞬間であり、虐待の過去に見きりをつけて新しい人生を歩みだそうとする出発の瞬間でもある。
ビリーは本当に、両親に会いに行ったのだろうか。レイラはビリーの臆病な心がつくりだしたガーディアンエンジェルではないか。げんにダンス教室に忍びこんだビリーには誰も気がつかない。ビリーがトイレで出くわした男の生徒はビリーの視線にたいする恐怖の権現に思える。狭苦しい部屋に住み電話の相手として出てくるだけのグーンもそうだ。あの小さな部屋はビリーの頭のなかにあるのではないだろうか。ダイナーで会ったビリーの片思いの相手ウェンディ(ロザンナ・アークェット)は、ビリーが愛を向ける対象から愛を得るどころか関心すらも引けず、それによって畏れと嫌悪の壁をつくってしまうパターンとして的確に機能している。唐突にあらわれるウェンディもまたビリーにだけ見える存在なのかもしれない。
そのような目で見ると、『バッファロー’66』は偶然に出会った男女が問題や困難を乗り越えて真に結ばれる純愛物語といより、虐待を受けて大人になった男が想像のちからを借りて過去と対峙し、自分の人生をつかみとっていく再生の物語のようにみえてくる。私はむしろこの見方のほうが好きだ。
作品情報
『バッファロー’66』(1999)
監督:ヴィンセント・ギャロ
出演:ヴィンセント・ギャロ、クリスティーナ・リッチほか
1998年
アメリカ合衆国
2021年1月29日より渋谷WHITE CINE QUINTOほか全国でリバイバル上映中
オフィシャルサイト
パンフ情報
ざらしとした手ざわりの中質紙
【奥付情報】
32ページ・B4定型
発行日:1999年7月3日
発行:株式会社キネティック
編集:キネティック+畑野裕子
デザイン:関口修男(PLUG-IN GRAPHIC)
印刷:株式会社金羊社
定価:1000円(税込)
https://twitter.com/Drafting_Dan/status/1360415073504616449?s=20
関連パンフ情報
『ハニーボーイ』(2019)
横長でハチミツを思わせるオレンジが基調。裏表紙のインパクト。
【奥付情報】
28ページ・A5定型
発行日:2020年8月7日
発行承認:ギャガ株式会社
編集・発行:松竹株式会社事業推進部
編集:石川天翔[松竹]
デザイン:新井匠
印刷:成旺印刷株式会社
定価:773円+税
https://twitter.com/Drafting_Dan/status/1360418218028896257?s=20