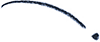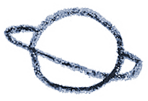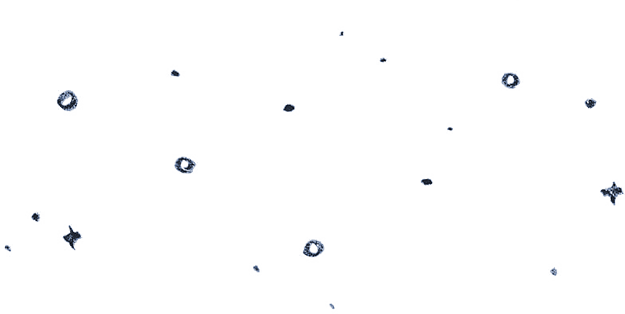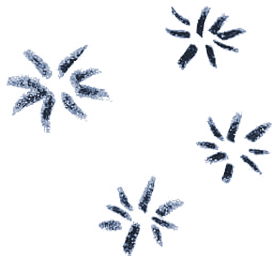文=竹美

日本最強のホラースポットは、樹海や恐山や犬鳴峠などではない。それは意外にもありふれたところにあった。日本人の半数以上が毎日出入りしている場所…職場である。
勤勉な「エコノミック・アニマル」(実は褒め言葉なのだそうで)によって支えられる日本の職場は、我慢と自己犠牲を内面化し、会社組織に順応した「われわれ」によって日々維持されている。本作は、実際に起きたセクシャル・ハラスメント事件をベースに、ある職場の「仲間」の会話を描いている。
ある大手ホテルで働く親しいメンバーが社員向け福利厚生施設と思われる家にやってくる。フロント業務のサキが、ネット上に個人情報を晒され、誹謗中傷を浴びているのを皆で慰めるためである。
本作が特によくできているなと感じたのは、何か問題が起きたときに「もうそういう暗い話をやめよう」「仲間を疑うのはよくないよ」「まずは「やってない」と信じよう」という、根拠のないポジティブムードを作ろうとする同調圧力が発生するタイミングである。目の前の問題をどうかするよりも、その場の空気を重くしないことの方が重要なのだ。
サキは、前半であれだけのことが起きた後に、ある人物から「無責任だ」「甘えるな」「自分の頭使えよ」と、まるでパワー・ハラスメントのようなことを言われる。「会社にも、この場の皆にも「迷惑」をかけたのに逃げるのか」というアレを、よりによってその人物に言わせるのが凄い。彼女を非難する人物自身は、自分は正しいこと、いいこと、世の理を教えている気になっているのだが、あの立ち位置・職業の人の無自覚な情報発信への批判だと受け止めた。我々は、そのような情報を目にし、他人の「痛み」を勝手にジャッジして「きれいごと」を消費しているのではないか…その意味でも怖いシーンである。
後半、サキが再び大問題に直面し、似たメンバーたちが彼女を「元気づける」ために集まるが、観る方が気が重い。今回は「ことを穏便にしつつ、彼女に仕事を続けさせたい」という会社側に立った女の先輩と、それまでは仲違いをさせないように「ことを穏便に」したがっていたかに見えた女の先輩が激突する。その下りは賛否あると思うが、何故彼女たちがぶつからねばならないのか、それに乗っかるのは誰なのか、誰が黙っているのか、見ものだ。
本作は恐らく、小津安二郎や木下恵介など昭和の日本映画を意識していると思う。そこで、本作で面白いのは、特に小津映画を観て気分良くなっていたであろう、中年の男性が、ある一度の決定的なシーンを除き、概念としてのみ存在していること。その方が怖さが引き立つ。そちら側の人達が何か言いたくなるとしたら、最初に出る一言こそがこの映画で追及したいテーマではないかと思う。
サキの受難は続き、後半では「男性に好意を一方的に寄せられる」問題にも直面する。何でも職場の問題を穏便に収めたがる先輩が、知らずに善意でその問題を助長してしまう流れも恐ろしかった。これは結構職場や学校等で起きているのではあるまいか。その問題が隠ぺいされたことで、要らない批判を浴びるサキ。もうその辺では苦しくなってきて、サキが包丁持ち出すシーンが欲しくなる。
途中、意外な形でゲイのカップルが登場し、陰鬱な作中で唯一さわやかな印象を残す。しかし、セクシャル・ハラスメントの問題について、ゲイは本当の意味では「女性の味方」ではありえないことも示している。所詮「男性」だから。女性とゲイの間にある温度差をよく描いたと思う。
「ちょっとくらい我慢するのが当然だ」と思い込み、「迷惑」を忌み嫌い、「重く考えるのやめようよ」と虚ろなポジティブ思考で誤魔化すことがまかり通っている職場は、監理する側から見れば大変ありがたい。現場が問題のもみ消しに協力的だからだ。それは所謂「忖度」ではないかと思う。国会やマスコミで盛んに問われた「忖度」とは、ときの権力者によって起きたトップダウンの問題ではなく、「われわれ」が日々何気なく自発的にやっている些細な判断のボトムアップ的な積み重ねである。そんなことを直視するのはつらいので、我々は「しかたない」という鎮痛剤を自分に打ち、ときの政権を声高に非難したのかもしれない。
私は本論では本作をジェンダーギャップの問題を描いた作品だとは書かなかった。何故なら本作が見せているものは、我々皆が何かしらの形で巻き込まれている、業務と関係ない感情労働の問題と直結しているからである。
日本の職場の問題を真正面から描いたスリリングかつ気が滅入る本作は、日本の家庭の中にある恐怖を描いた『来る。』(2018年/中島哲也監督)に匹敵する社会派映画だと思う。