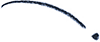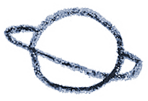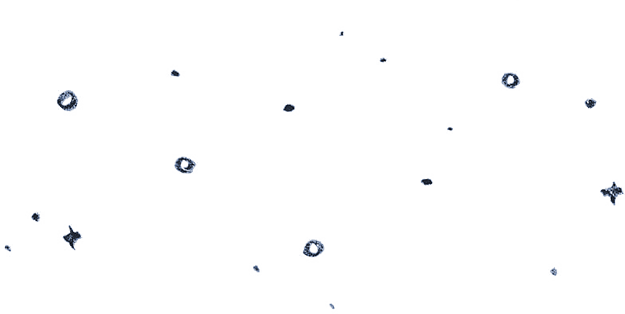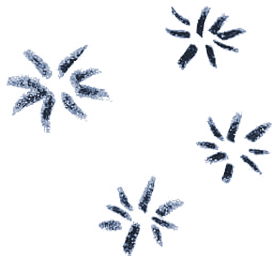文=竹美
「映画パンフは宇宙だ」の『Us[アス]』Fan Zineは、日本の我々はどんな問題を底に持っているのだろう…と最後に問いかける形にして終わった。それについて私なりに発信すべきと考え、『おくりびと』(2008年/滝田洋二郎監督)と『来る。』(2018年/中島哲也監督)のことを考えてみたいと思う。
差別肯定の映画がオスカーもらっちゃってびっくり
前者は世界的な評価を受けて我々日本人も随分いい気持ちになった映画。私は同作をヒットの数年後に何気なく見た。途中、広末涼子演じる主人公の妻が「触るな、穢らわしい!」と叫んだ時、電気が走ったような気持ちになった。
うわっ!これ差別の映画だ!
歴史の深さを感じさせる職業差別が生理的嫌悪感として表出しているのだと思う。ムラ社会の中で人目を気にして疎遠になる友達。最初は「ヘイト」しまくっていたのに手のひら返したように葬式の後に納棺師を尊敬する人々。私はちょっと引いたが、それを何と言うでもなく受け入れる、本木雅弘演じる主人公の尊いんだが鈍感な姿って…こうあってほしい被差別者のありようなのだなと思った。社会を恨むな、ひたすら耐えろ、いつか思いが通じる。そして、頑張っている人が報われる物語に弱く、そこに歴史的なニュアンスを示唆する差別があることに全く頓着しない観客=我々がいる。
しかしながら、あのお話の中ですら救いを得られなかった人がいる。余貴美子演じる葬儀屋で働く女である。彼女は子供を置いて逃げて来た罪を背負っているが、そちらに対しては全く容赦のない映画である。また、広末涼子の妻のキャリアとか何とかが殆ど顧みられていない。笑顔の張り付いたような彼女の存在感…自分に与えられた役を演じる自我の薄い女というあり様は、日本では広く受け入れられているが、ぼちぼち自我に気が付き始めた平成令和の日本の我々は、そんなことをすると遅かれ早かれ限界が来てキレたり病んだりすると知っている。本作では勝手な夫にキレることがぎりぎり許された。子供を妊娠すると、子をダシに使って夫を支配しようと画策する妻。悪役扱いだがしかし、それ以外に彼女に選べる手段が無いのではないか。「自分を犠牲にして夫に尽くす私」を選ぶことは、そもそもが負け戦なのだと思う。
不公平に怒る妻が手にする「差別」
ところで、穢らわしい、という言葉、日本では差別の正当化手段としてしか耳にしないし、あの言葉がトリガーになって辛い人もいるので、今後映画の中で使うのは止めたらどうだろう。
聞くのも嫌だから、その言葉を禁止して!
その場所から逃げられない人にとっては必死の叫びだ。でも、広末涼子妻にしてみれば「私を幸せにすると言ったくせに何だよこの人生!?あんたの勝手でこんなとこ来て、こんな仕事しやがって…何だよこの仕事!」と言いたくもなるだろう。彼女は、そこに「差別」が転がっているから、怒りのあまり、それを手にとって投げ付けただけなのだとも言える(地獄…)。
ラストシーンも、夫の側に寄り添ったシーンだと考えると、あの家族の未来も心配になってくる。子供の人生を支配し夫に抵抗したりできれば支配することくらいしか、あの生き方を選んだ彼女が留飲を下げる手段はない。あの生き方を止める=離婚という手段もあるが、一度仕事を辞めた女にとってはあまりに険しい(ほんと地獄…)。
ぼぎわんが「来ちゃった♥」
さて、そんな感じで不公平をはらんだ若くて幸せいっぱい家族には一体何が待ち受けているか?この2ちゃんねる的な、ゲスな興味を見事にホラー映画にしたのが『来る。』。アメリカンやばい家族映画が『ヘレディタリー 継承』(2018年/アリ・アスター監督)ならば、日本はこれ!
主演の妻夫木聡は、大事なものを失ってから何かに気がつく手遅れ男役が続いているが、同作の彼もまた、無邪気に自分に与えられたリソースを消費し、楽しく生きている。一方、彼の幸せ一家演出に疲れ果てている妻の黒木華。彼女のシーンはつらかった。ずっと親から逃れたかったから、手にしたものが最高なのだと思いたいのに、どうも違和感がぬぐえない。不公平な社会状況を踏まえた妻の怒りの猛チャージ描写が見事。壊れますよ…人の世話しながら自分のこともやるなんてできないもん…。乗っかっている夫に悪意は無い。だからこそ、真実に対面した夫は無傷ではいられず、またしても手遅れ男になってしまう妻夫木聡がちょっと哀れである。
同作に登場する妖怪、ぼぎわんは、我々の中に巣食っている欲望アラートだろうか。あれは、事情を斟酌せずに無差別に、度を越した欲を持った者に制裁を加えに来る。何と苛烈な。松たか子さんの存在が頼もしいが、超然としていて、日本というか人間社会そのものを心底嫌っているようにも見える。
黒木華妻は夫に搾取されつつ、不本意にも虐待の連鎖を生んでしまう哀しい女である。私は、彼女が死んだシーンは、不憫過ぎて泣けた。こんな風に生きるつもりじゃなかったよね…幸せになりたかったのに…でも、彼女にどういう救いがありえたんだろうかと考えると更に落ち込む。
昭和の残りかすと我慢共同体
結構多くの人が、冒頭の親族の集まりシーンが嫌だった、と言っている。昭和中期の松竹映画なら何てことない平和で楽しい空間が、実は高齢の男性以外は皆無理していないか?と問い直されている。特に若い女性にとって、実家への帰省はもはやホラーなのだ。昭和期ならば、裏で舌出してたり、長年の冷遇に耐えかねて田舎捨てて都会に出てったり、杉村春子だったり岡田茉莉子だったり、何らかのガス抜きがあったのだが、平成の我々にそんなものは無い。結局、昭和期もだいぶ呪いをはらんでいたのだ。
サイズの合わない服を着て
社会はうっとおしい。サイズの合わない服みたい。でも着ないと外には出られない。服を着て外に出るということは、そのルール、常に窮屈な服を着るという仕組み全体=社会の今に加担していることになるんだぞ!と社会学者に教えられたところで、多くの場合、会社や学校には行かなきゃいけないし、あんまり嬉しくもないし、単に今まで我慢してきた自分の愚かさに腹が立ってくるか、もっと利口に立ち回ってやろうと心に決めるだけである。服を着て社会に出ないと決める行者の生き方もありだし、常に社会に中指立てて生きるパンクの生き方もありだ。
怒ることも大事だと思う。私は社会性が少し足りないので、学校も会社も上下関係も体育祭も嫌いだし、会社とか上司の理不尽に腹が立ちやすいので、あんまり偉くはなれない。それでも男なのでまだマシなのだろうとも考える。「生きているだけで差別に加担してしまう、こんな世界、要らない」と言っている人も沢山いて、そちらに引っ張られる自分もいるが、懸命に生きようとしている人も、人を助けたり、世界をよくしようとする人も沢山いるということも知っている。中途半端でどっちつかずのままだらしなく生きている。
痛みを訴える声をよく聞いてみよう。不快に聞こえるかもしれない。なぜ何もしてない私が怒られないといけないのかと。でも、反発したくなったり、不快であるほど、「私たち」の真実を突いているのだと思う。一神教のように、絶対的な存在の前にひれ伏し己を点検する習慣のない私たちは、自省なんかほとんどしない。暴動や略奪に至る程社会が荒れていない今のうちに、できることをやっておいた方がいいのではないだろうか。